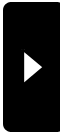2016年04月20日
本を貸すバカ返すバカ?
タイトルは5年前に地元の山口県にUターンし、某地方銀行に中途で入行した際、当時の支店長で男気満載なかたと飲んだ時に、教えてもらった言葉です。採用が決まったあとの面接で「君を採用した決めては、履歴書の趣味欄に読書とあったからだよ。最近の若い行員は本をろくに読まず、お客さんと話するにも話題がないからね。私の支店では月に1冊は本を読むというノルマを課している。おすすめの本があったら教えてあげてね」とも言われました。
東京にいた頃、在籍した会社の先輩で、東京工業大学の大学院で原発のエンジニアリングの勉強をしていたのに、なぜかかつての長期信用銀行のひとつに就職したという変わり種のかたがいました。かなりの読書家で、ある時、「お前はこの本を読むべきだ」と何冊か勧められたことがあります。そのひとつでタイトルは忘れましたが、脳神経関連の学者さんが書いた、脳は所詮神経の一部なので、脳だけが思考している訳ではなく、脳ごときに支配されてはならないという内容の新書でした。驚いたのは同じ本を3冊買われていたことでです。実物を見せられて、てっきり1冊貸してくれるか、譲ってくれるものかと思っていたら、会社の近くにある本屋に昼休みに私を拉致し、これを買えと言われました。しぶしぶ購入したものの、なかなか面白かった記憶があります。
その先輩の持論では、「テレビ番組と同様に、世の中には、読むべき価値のある本は希少で、しかもあまり売れてないことが多い。」それでそのかたは、本当にいいと思った本を見つけたら、著者に敬意を表して、少なくとも3冊は購入し、知り合いにも買わせるようにしているそうでした。そうしないといい本を書くひとの経済生活が成り立たなくなることも可能性としてはあり、ただでさえ希少な良書を書くひとがいなくなるのが理由とのことでした。
まあ、気持ちはわかったのですが、私はすでに持っている本を勘違いして再度購入したことはあるものの、3冊は買ったことはありません。本を内容ではなく見た目の綺麗さで価値判断するブックオフで本買うのも、その論理ではダメなのかな…
東京にいた頃、在籍した会社の先輩で、東京工業大学の大学院で原発のエンジニアリングの勉強をしていたのに、なぜかかつての長期信用銀行のひとつに就職したという変わり種のかたがいました。かなりの読書家で、ある時、「お前はこの本を読むべきだ」と何冊か勧められたことがあります。そのひとつでタイトルは忘れましたが、脳神経関連の学者さんが書いた、脳は所詮神経の一部なので、脳だけが思考している訳ではなく、脳ごときに支配されてはならないという内容の新書でした。驚いたのは同じ本を3冊買われていたことでです。実物を見せられて、てっきり1冊貸してくれるか、譲ってくれるものかと思っていたら、会社の近くにある本屋に昼休みに私を拉致し、これを買えと言われました。しぶしぶ購入したものの、なかなか面白かった記憶があります。
その先輩の持論では、「テレビ番組と同様に、世の中には、読むべき価値のある本は希少で、しかもあまり売れてないことが多い。」それでそのかたは、本当にいいと思った本を見つけたら、著者に敬意を表して、少なくとも3冊は購入し、知り合いにも買わせるようにしているそうでした。そうしないといい本を書くひとの経済生活が成り立たなくなることも可能性としてはあり、ただでさえ希少な良書を書くひとがいなくなるのが理由とのことでした。
まあ、気持ちはわかったのですが、私はすでに持っている本を勘違いして再度購入したことはあるものの、3冊は買ったことはありません。本を内容ではなく見た目の綺麗さで価値判断するブックオフで本買うのも、その論理ではダメなのかな…
2016年04月20日
お水の組合?
この内容は、以前、どこかで書いたような気もしますが、なぜか思い出したのでまた書いてみます。
東京に住んでいたころ、通勤途中の電車の中刷り広告で、新宿の歌舞伎町のキャバ嬢が有志の集まりで組合を作ったというのを見たことがあります。よく給与不払いとかで問題になっていたようで、キャバ嬢の権利を守るために、どこかの弁護士さんが協力していたようです。
30代半ばのころ、ほぼ毎日キャバクラや会員制クラブに出入りして仕事のストレスを解消していました。当時、FPの資格を、会社の昇格要件だったことが理由で取りましたが、あるキャバ嬢から「私も今度FPの試験受けますよ!3級!最近、キャバ嬢仲間でFPの勉強するのが流行ってるんですよ」という話を聞きおどろいたことがあります。
昨年まで、福岡市博多区に住んでましたが、よく週末に中洲で飲むことがありました。キャバクラやラウンジ、ガールズBAR(ガールス居酒屋というのも見つけました)も男の嗜みとしてたまに行きました。しかし、どんな場所(たとえ場末のスナックでも)かつて新宿の歌舞伎町であったらしい、彼女たちの待遇面などで問題はないのですかね。どこかの弁護士さんや税理士さんとタッグをして、お水の女性専門のよろす相談的なFP事務所など、ニーズはあるでしょうか?お水の女性による投資組合など面白そう…お水の顧客から様々な情報を集めて投資に生かすなど(インサイダー?)。はい!数年前に地元の山口県にいた時に思いついたものの、特に具体的な行動は起こしておりません。
しかし新宿歌舞伎町のキャバ嬢組合ってちゃんと機能して存続しているのかな?
ちなみに私は3年ほど当時いた会社で組合活動してました。経営陣と丁々発止してなかなか面白かったです。以前、ブログに書いたのでURLを載せます。
http://schole.chesuto.jp/e1378882.html
東京に住んでいたころ、通勤途中の電車の中刷り広告で、新宿の歌舞伎町のキャバ嬢が有志の集まりで組合を作ったというのを見たことがあります。よく給与不払いとかで問題になっていたようで、キャバ嬢の権利を守るために、どこかの弁護士さんが協力していたようです。
30代半ばのころ、ほぼ毎日キャバクラや会員制クラブに出入りして仕事のストレスを解消していました。当時、FPの資格を、会社の昇格要件だったことが理由で取りましたが、あるキャバ嬢から「私も今度FPの試験受けますよ!3級!最近、キャバ嬢仲間でFPの勉強するのが流行ってるんですよ」という話を聞きおどろいたことがあります。
昨年まで、福岡市博多区に住んでましたが、よく週末に中洲で飲むことがありました。キャバクラやラウンジ、ガールズBAR(ガールス居酒屋というのも見つけました)も男の嗜みとしてたまに行きました。しかし、どんな場所(たとえ場末のスナックでも)かつて新宿の歌舞伎町であったらしい、彼女たちの待遇面などで問題はないのですかね。どこかの弁護士さんや税理士さんとタッグをして、お水の女性専門のよろす相談的なFP事務所など、ニーズはあるでしょうか?お水の女性による投資組合など面白そう…お水の顧客から様々な情報を集めて投資に生かすなど(インサイダー?)。はい!数年前に地元の山口県にいた時に思いついたものの、特に具体的な行動は起こしておりません。
しかし新宿歌舞伎町のキャバ嬢組合ってちゃんと機能して存続しているのかな?
ちなみに私は3年ほど当時いた会社で組合活動してました。経営陣と丁々発止してなかなか面白かったです。以前、ブログに書いたのでURLを載せます。
http://schole.chesuto.jp/e1378882.html
Posted by 木原 昌彦 at
11:09
│Comments(0)
2016年04月20日
歩こう!歩こう!私は…〇〇(任意の文字列)
以前、北九州の門司港に出張したとき、スマホでBARを検索したら、とあるBARのfacebookページが出てきました。中身を見ると、知り合いのチェックイン履歴が出てきたので、懐かしく思い出し、そのBARに入りました。
その知り合いに最後に会ったのはおそらく10年以上前だと思います。当時、東京の武蔵野市に住んでいて、吉祥寺にあるChicagoというダーツBARにたまに行っていました。彼はそこでBartenderとして働いてました。風貌は背が高く、イケメンでしたが、話をすると関ジャニ系の面白い人でした。そのBARはBartender在籍者が多く、顔は覚えても名前を覚えるのが苦手な私は、何度か顔を合わせたにもかかわらず、ある時、彼にこう聞きました。
私 「そういえば、あなたはお名前なんだっけ?」
彼 「ええ!まだ名前覚えてくれないのですか?」
私 「すまん!私は江戸っ子ではないけど、宵(酔い?)越しの記憶は持たないのだよ」
彼 「まあ、いいです。私の名前なんか覚える必要ないですから!」
私 「そんなに卑屈になることはないと思うけど」
彼 「実は、この店は今日で最後なんですよ」
私 「え?辞めちゃうの?」
彼 「はい!明日から旅に出ます」
私 「そうなんだ!どこに行くの?」
彼 「今までお話しませんでしたが、実は私こういうものです」
名刺を渡されました。表記は「住所不定無職…○○○○(名前)」
私 「何これ?こんな名刺初めて見たよ!あなたは一体何者?」
彼 「実は、以前、歩いて日本を一周したことがありまして、その体験談を本にしました。明日から2周目に入ります」
私 「そうなんだ!2週目は逆回りとか?逆うち?それでその本はどこで買えるの?」
彼 「いえ、また同じ周りかたですよ…本はここに在庫がございます」
私 「じゃあ、それ買うよ」
彼 「ありがとうございます」
1年後くらいに同じBARでBartenderとして働いてる彼に会いました。
私 「2週目から帰ったんだ。それで2冊目の本は?」
彼 「既にここに在庫がございます」
私 「じゃあ、それ買うよ。ところで3周目はいつから?」
彼 「まだ未定ですが、ちょっと疲れたので次はバイクにします…」
本日は大人の事情で会話形式でございます。
最後に彼の本の紹介URLですが、試練編のあとは冒険編とか挫折編とかあるものかと思っていたら完結編…
追伸:現在彼は大阪でカフェのオーナーをされているそうで、彼のお店のfacebookページのURLは以下のとおり…
https://www.facebook.com/meguruteam?pnref=lhc
その知り合いに最後に会ったのはおそらく10年以上前だと思います。当時、東京の武蔵野市に住んでいて、吉祥寺にあるChicagoというダーツBARにたまに行っていました。彼はそこでBartenderとして働いてました。風貌は背が高く、イケメンでしたが、話をすると関ジャニ系の面白い人でした。そのBARはBartender在籍者が多く、顔は覚えても名前を覚えるのが苦手な私は、何度か顔を合わせたにもかかわらず、ある時、彼にこう聞きました。
私 「そういえば、あなたはお名前なんだっけ?」
彼 「ええ!まだ名前覚えてくれないのですか?」
私 「すまん!私は江戸っ子ではないけど、宵(酔い?)越しの記憶は持たないのだよ」
彼 「まあ、いいです。私の名前なんか覚える必要ないですから!」
私 「そんなに卑屈になることはないと思うけど」
彼 「実は、この店は今日で最後なんですよ」
私 「え?辞めちゃうの?」
彼 「はい!明日から旅に出ます」
私 「そうなんだ!どこに行くの?」
彼 「今までお話しませんでしたが、実は私こういうものです」
名刺を渡されました。表記は「住所不定無職…○○○○(名前)」
私 「何これ?こんな名刺初めて見たよ!あなたは一体何者?」
彼 「実は、以前、歩いて日本を一周したことがありまして、その体験談を本にしました。明日から2周目に入ります」
私 「そうなんだ!2週目は逆回りとか?逆うち?それでその本はどこで買えるの?」
彼 「いえ、また同じ周りかたですよ…本はここに在庫がございます」
私 「じゃあ、それ買うよ」
彼 「ありがとうございます」
1年後くらいに同じBARでBartenderとして働いてる彼に会いました。
私 「2週目から帰ったんだ。それで2冊目の本は?」
彼 「既にここに在庫がございます」
私 「じゃあ、それ買うよ。ところで3周目はいつから?」
彼 「まだ未定ですが、ちょっと疲れたので次はバイクにします…」
本日は大人の事情で会話形式でございます。
最後に彼の本の紹介URLですが、試練編のあとは冒険編とか挫折編とかあるものかと思っていたら完結編…
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】泣き虫男、歩いて日本一周してきます [ 中林あきお ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7779%2f77790369.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f7779%2f77790369.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】泣き虫男、歩いて日本一周してきます [ 中林あきお ] |
 【楽天ブックスならいつでも送料無料】泣き虫男、歩いて日本一周してきます(完結編) [ 中林あ... |
追伸:現在彼は大阪でカフェのオーナーをされているそうで、彼のお店のfacebookページのURLは以下のとおり…
https://www.facebook.com/meguruteam?pnref=lhc
2016年04月19日
適当?最適?
以前、前世が高田順次氏という設定にしていました。
「適当」という言葉が某氏にはよく使われますが、適当とは、「適していて当たっている」と書くので、おそらく本来はネガティブな意味ではないのではないかと考えています。
同様に誤った(?)使い方となった言葉で「微妙」というのがあります。本来はたしか仏教用語で「細かいところまで行き届いた絶妙な状態」ということだったかと記憶しています。もっとも、言葉は生き物らしいので意味が変わってくるのはしたかないことなのかもしれません。
最適という言葉もありますが、全体の最適のためには部分の最適が後回しになることも多いですね。もっとも、全体をどこに設定するかという問題もあります。会社全体なのか、一部門なのか、一個人なのか…国とか地球という全体設定も有り得ます。
人類が生き残る必要があるのかどうかは全くのところ疑問です。基本的に滅びる時は滅びるだけの原因があるので、その時はその時と思っています。いわゆる適者生存でしょうか。
何かの答えを出す前には、問題の設定というか、前提条件と目的、そして優先順位が必要かと考えています。
それさえ決定すればほとんどの問題は数学的に、もしくは論理的に答えが出るものと思います。
人間が悩むのは、目的と優先順位が定まっていない時ではないでしょうか?
それぞれ価値観(価値感?)が違えば目的も優先順位も異なりますので、闘争が発生するのかと思われます。
私も自分の目的は具体的ではないですが、まあ幸せになりたいのでしょうか。でも、自分がどういう状態が幸せなのかはよくわかりません。でも毎日楽しければいいのではないかと思います。嫌なことは翌日に持ち越さず忘れることが大事なのかも。
おててのシワとシワを合わせて…シワヨセ…南無三!切羽!一休さん!一休み一休み…
「適当」という言葉が某氏にはよく使われますが、適当とは、「適していて当たっている」と書くので、おそらく本来はネガティブな意味ではないのではないかと考えています。
同様に誤った(?)使い方となった言葉で「微妙」というのがあります。本来はたしか仏教用語で「細かいところまで行き届いた絶妙な状態」ということだったかと記憶しています。もっとも、言葉は生き物らしいので意味が変わってくるのはしたかないことなのかもしれません。
最適という言葉もありますが、全体の最適のためには部分の最適が後回しになることも多いですね。もっとも、全体をどこに設定するかという問題もあります。会社全体なのか、一部門なのか、一個人なのか…国とか地球という全体設定も有り得ます。
人類が生き残る必要があるのかどうかは全くのところ疑問です。基本的に滅びる時は滅びるだけの原因があるので、その時はその時と思っています。いわゆる適者生存でしょうか。
何かの答えを出す前には、問題の設定というか、前提条件と目的、そして優先順位が必要かと考えています。
それさえ決定すればほとんどの問題は数学的に、もしくは論理的に答えが出るものと思います。
人間が悩むのは、目的と優先順位が定まっていない時ではないでしょうか?
それぞれ価値観(価値感?)が違えば目的も優先順位も異なりますので、闘争が発生するのかと思われます。
私も自分の目的は具体的ではないですが、まあ幸せになりたいのでしょうか。でも、自分がどういう状態が幸せなのかはよくわかりません。でも毎日楽しければいいのではないかと思います。嫌なことは翌日に持ち越さず忘れることが大事なのかも。
おててのシワとシワを合わせて…シワヨセ…南無三!切羽!一休さん!一休み一休み…
Posted by 木原 昌彦 at
20:49
│Comments(0)
2016年04月19日
成功体験・失敗談の効用?
最近は悩むことが少なくなりました…でも若い頃は(今思えば)瑣末なことで悩んでいたような気がします。人生は選択の連続なので、どのようなプロセスを経たとしても、結果として何かを選ぶしかありません。
ところで、ハタからどう見えるか(正直そんなことどうでもいいですが)は別として、自分としてはこれまで失敗の連続でした。ごくたまに思い通りになったこともありますが、努力したというより、好きなことをやっていただけなので、まあ要するにラッキーだったのだと思われます。
最近、若い人に、悩み事を相談された時思うことは「うーん…別にたいした悩みではないなあ。死ぬ訳ではないし、そんなことどうでもいいような気がする。でも俺も若い頃、似たようなことで悩んでたなあ。悩まなくなったのは、単なる慣れだろうか…心の傷(小心者で傷心者!)にかさぶたついて保護しているのだろうか。これが、鈍感力、老人力なのか…うーん悩むなあ」という感じです。
結果として伝えるのは、自分の失敗談です。世の中は How to Success(成功本?性交本は? How to S…) の本がやたらとあり、まあ参考になりそうなものもありますが、成功者の本を読み、同じことをしたからといって成功する確率はそれほど高くないかと想像します。また、環境が変化しているのに過去の成功体験に固執すると失敗したりもします。もっとも、厳密な統計をとったわけでもないので、このブログのタイトルどおり気のせいです。逆に失敗をした場合は、単に不可抗力的なアンラッキーである場合もありますが、多くのケースでは、それなりに原因があるような気もします。成功者の真似をして成功する確率と失敗者の真似をして失敗する確率…どちらが高いと思われるでしょうか?
なので、「こういう状況でこういう判断をし、こう行動したら、こんな失敗したんだよ。だから君は俺と同じ失敗をする必要はないんだよ」という方向に持っていきます。投資では、勝つことは素晴らしいことかもしれませんが、継続する(つまり生き続ける)ためには、負けないことのほうが重要かと考えています。株式投資の格言(ほとんどは無内容なインチキな気がしますが)に「当たり屋につけ、曲がり屋に向かえ」というものがあります。しかし、うくいった投資手法をよってたかってみんなで真似をするとその有効性が薄れるケースもままあります。
また、フランスの哲学者サルトルの実存主義は、生まれたてきたこと自体にたいした理由はないし、生きていることにもたいして意味はないものの、まあそれでも生まれてきてしまって、生きているのでとりあえず何かしようという意味合いのようで、チャレンジしてみるというのも気が楽かもしれません。昔所属した会社のインテリ後輩が「まあ所詮、人生なんて暇つぶしですよ」と言っていたことも思い出しました。
最後に逃げ口上ですが、若い人!悩みがあるなら悩んでください。簡単に正解(そんなものは無いような気もしますが)を教えてもらえるとは思わず…さんざん悩んだ結果…何かが残るような気がします…
またとりとめのないことを書いてしまった…(石川五右衛門風に)
ところで、ハタからどう見えるか(正直そんなことどうでもいいですが)は別として、自分としてはこれまで失敗の連続でした。ごくたまに思い通りになったこともありますが、努力したというより、好きなことをやっていただけなので、まあ要するにラッキーだったのだと思われます。
最近、若い人に、悩み事を相談された時思うことは「うーん…別にたいした悩みではないなあ。死ぬ訳ではないし、そんなことどうでもいいような気がする。でも俺も若い頃、似たようなことで悩んでたなあ。悩まなくなったのは、単なる慣れだろうか…心の傷(小心者で傷心者!)にかさぶたついて保護しているのだろうか。これが、鈍感力、老人力なのか…うーん悩むなあ」という感じです。
結果として伝えるのは、自分の失敗談です。世の中は How to Success(成功本?性交本は? How to S…) の本がやたらとあり、まあ参考になりそうなものもありますが、成功者の本を読み、同じことをしたからといって成功する確率はそれほど高くないかと想像します。また、環境が変化しているのに過去の成功体験に固執すると失敗したりもします。もっとも、厳密な統計をとったわけでもないので、このブログのタイトルどおり気のせいです。逆に失敗をした場合は、単に不可抗力的なアンラッキーである場合もありますが、多くのケースでは、それなりに原因があるような気もします。成功者の真似をして成功する確率と失敗者の真似をして失敗する確率…どちらが高いと思われるでしょうか?
なので、「こういう状況でこういう判断をし、こう行動したら、こんな失敗したんだよ。だから君は俺と同じ失敗をする必要はないんだよ」という方向に持っていきます。投資では、勝つことは素晴らしいことかもしれませんが、継続する(つまり生き続ける)ためには、負けないことのほうが重要かと考えています。株式投資の格言(ほとんどは無内容なインチキな気がしますが)に「当たり屋につけ、曲がり屋に向かえ」というものがあります。しかし、うくいった投資手法をよってたかってみんなで真似をするとその有効性が薄れるケースもままあります。
また、フランスの哲学者サルトルの実存主義は、生まれたてきたこと自体にたいした理由はないし、生きていることにもたいして意味はないものの、まあそれでも生まれてきてしまって、生きているのでとりあえず何かしようという意味合いのようで、チャレンジしてみるというのも気が楽かもしれません。昔所属した会社のインテリ後輩が「まあ所詮、人生なんて暇つぶしですよ」と言っていたことも思い出しました。
最後に逃げ口上ですが、若い人!悩みがあるなら悩んでください。簡単に正解(そんなものは無いような気もしますが)を教えてもらえるとは思わず…さんざん悩んだ結果…何かが残るような気がします…
またとりとめのないことを書いてしまった…(石川五右衛門風に)
Posted by 木原 昌彦 at
19:39
│Comments(0)
2016年04月19日
ゆとりかスパルタか…

ゆとり教育というのが以前ありましたが、どうも結果は思わしくなかったようです。たしか個性を伸ばすというのもテーマにあったような気がします。
導入当時既に社会人でした。個性を伸ばすっていったい何なのかよくわかりませんが、同僚とそのことを話題にした時、以下のような意見が出ました。
・ひとを大雑把に分けると、言われなくてもする人 言われたらする人 言われてもしない人の3種類で、ゆとりの結果、言われたらするひとが言われないためにしなくなる。
・学校制度や教育方針、受験勉強などで潰れてしまう程度の個性(?)は、所詮中途半端なので、早いうちに潰してあげたほうが、本人や社会全体のためには良い。
・詰め込み教育を批判するひともいるものの、一定以上はインプットしていないと創造的なアイデアなどは出てこない。
当時も好意的に受け止める人はあまり私の周りにはいませんでした。
私は、家庭教師や塾の講師のアルバイトをしたことしかなく、本職の教員でもなければ、子供もいないので取り立てて教育方針などに関心を持ったことはあまりありません。そして厳密な検証をしたこともないので、単なる気のせいか、思いつきです。
ずいぶん前ですが、日本の弁護士試験の制度が変更(法科大学院ができる前だったかな?)され、たしか受験回数に制限が出来たという記憶があります。その時、働きながら何度も受験して合格を目指す社会経験豊かなひとを排除するのかという批判もでたようですが、社会経験が豊かなのではなくて、単に受験経験が豊かなだけという反論もありあした。
学生時代にたまたま受けた一般教養で、フランスの教育制度というのがテーマにありました。フランスは徹底したエリート養成機関である、グラン・ゼコールという専門学校(別名ENAだったかな?)のようなものがあり、ソルボンヌなどのような伝統のある大学よりも難関とのことです。もっとも、医学とか哲学などは対象外で、日本でいうと高専のようなもののようです。政治家や大企業の経営者などはグラン・セコール出身者が多いようです。ところで、エリートという言葉はフランス語ですが、もともとはあまりいい意味でもなかったようです。フランスなどの欧州は、階級社会的なところがあり、エスタブリッシュメント(にわかセレブなどとは異なる)から見ると、有能かもしれないが、どこの馬の骨だか分からないといった差別用語だったようです。まあ、学業と人格形成や品格というのは別のものなのかもしれません。
はい!なんでこんなこと書いているのかよくわかりませんが、ブログのタイトルどおり、暇人の気のせいなので…ちなみに大雑把に分けたとき…私は気が向いたらするひと…論外かな?そういえば、記事のタイトルに挙げた、スパルタのことを書くの忘れてましたが、まあいいか…ゆとりの後は悟りらしいですね…仏陀が再来?
2016年04月17日
成長を愚弄する?

よく周りに言っていることですが、私は癒し系ならぬ、冷やし系です。言動がその場を冷やしたりすることがままあり、夏場にはもってこいかと考えておりますが、意識的にリミッターをかけていないと(つまり自然体)、人の話の腰を折ってしまうこともあ多々あります。やはり、コミュニケーションを円滑にするには、なるべく人の話の腰は揉むようにしたいと思っています。
ところで投資にはいろいろな対象や手法、スタイルといったものがあります。株式投資に限定すると、投資目的はインカムゲイン(配当)とキャピタルゲイン(値上がり益)の獲得となるかと思います。前者はとりあえず多くの場合、比較的安定的ではありますが、後者は不安定で、ほぼ(?)予測が不可能とも言えます。
株価の変動には、外部要因も多く考えられますが、結局のところ当該企業の(1株あたりの)利益水準とその成長期待に寄ると考えられます。つまり株価が上がるには、単純には企業が成長する必要があるということです。
一昔前(?)の証券マンのセールストークには、「お客さんに夢を買ってもらう」というテーマがありました。勧める投資対象の企業や業界、国(外国の株や債券を組み入れる投資信託などの場合)のバラ色の未来を説明するということです。しかしながら、結果がともなうことは少ないケースです。なぜなら、将来に対する明るい情報は既に水面下で(?)出回っていることが多く、価格に織り込まれていることがままあるからです。「夢を望む」と書いてムボウと読んだりすることもありますが、末端の営業マンの話や新聞記事、ニュースで放送される内容には、投資価値のある情報としては、ほぼ最終局面を示すのみという場合が多く見受けられます。
また、高い戦略性を持ったビジネスモデルを有する企業もあるものの、それが成功するかどうかは、多くの不確実性をクリアする必要があり、実はコントロールできないことのほうが多いとも感じられます。よく言われることですが、できない理由はいくらで出せるものの、それを実現させるというアイデアは希少かもしれません。もちろん、アイデアがあるということは重要ではありますが、当然のことながらリスクがあり、成功や成長の期待が高いほど、それが裏切られた時の落胆は大きく、株価の値下がり率も大きくなると思われます。こういった理由で、成長(すると思われる)株に投資するのはリスクが高いということになります。
成長株投資をグロース(Growth)投資と表現することが資産運用業界では一般的です。私はアナリストという仕事をしていたころ、正直、このグロース投資というスタイルに疑問を持っていました。理由は企業を取材したり、機関投資家向け説明会などで、仮にポジティブな話を聞けたとしても、そんな情報は自分だけが持っている訳ではなく、また、自身の企業分析で有望な銘柄かと思うことはあっても、その成長プロセスの実現には多くの前提条件があるだけでなく、結果としての証券投資では、確率論的には五分五分と思えました。そのため、自分自身のスタイルは徐々に割安株、いわゆるバリュー(Value)投資へと導かれました。大儲けは期待できないものの、負ける確率が低いほうを選んだということです。バリュー投資では、証券分析の父と言われているベンジャミン・グレアムや、その弟子で著名な投資家のウォーレン・バフェットがいます。面白みはないかもしれませんが、非常に合理的ではあると、彼らの著作等を読んでいて感じました。
成長株を見つけることは楽しいですね。結果を出すのは非常に困難ですが…ちなみに私は第3次性徴期です…
2016年04月16日
コンサルタントの価値?

たしか、以前やっていたブログでも似たようなことを書いた記憶があります。
コンサルタントという職種がありますね。世間には様々なコンサルタントが存在し、アドバイスの対象はいろいろありますが、現実問題として玉石混交かなと思われます。
昔からある業種で実績がわかりやすいものならいいのですが、新しい分野だと、実績の評価も難しく、入門書に産毛が生えた程度の内容でフィーを取ろうとする不届きな(?)かたも散見されるようです。しかし、そんなアドバイスでも全く知らないことであれば有難いのかもしれませんし、顧客が門外漢なのであればコンサルタントの質を見極めるのは難しいのかもしれません。知り合いの経営者にはコンサルタントなんて胡散臭いと言っているひとも多いのですが、全てがそうだとはもちろん思いません。やはり、なんちゃってコンサルタントの存在がコンサルタントという仕事自体にネガティブな印象を与えているのかもしれません。もっとも、どのような専門職でもなんちゃってレベルの存在はあるかとも考えられます。
昔の上司で生真面目で優秀、しかも人格者なかたがいました。当時の私は言いたいこと言い放題の不肖の部下でしたが、そんな私でもよくしてもらいました。私のように偏見と思い込みの塊などではなくて、バランスの取れた理知的なかたでした。当時の部署は経営企画室のようなところでしたが、様々な部署からの現場の状況や意見などをヒアリングをした上で提案した経営方針案は、当時の社長から却下されました。その後、外資系のコンサルタントファームに結構高いお金を払って、アドバイスを受けたことがあったのですが、その内容が、上司が作成されたものとほとんど同内容でした。高額の報酬と引き換えに社内で作ったものと代わり映えしない内容に少しがっかりした反面、我が意を得たりと思われたようでした。そしてそのコンサルタントの意見は採用されました。ちなみにその上司は数年後、社長と喧嘩して退社し、国内監査法人系の大手コンサルタント事務所に転職されました。
そんなことがあった数年後、ある外資系(KPMGだったかな)コンサルタントファーム主催のセミナーで、若手のコンサルタントの講演を聞いたことがあります。なかなか良い内容だと思ったので、懇親会の席で話しかけ、昔の上司の話をしたら、そのコンサルタント君はため息をつきました。彼曰く「実は、私も顧客のために役に立とうと思って努力しているつもりなのですが、顧客が大企業だったりすると、既に方針の結論は決まっていることも多く、実質的なアドバイスの提供としてのコンサルタントの出る幕はない場合もあります。それでもコンサルタントを雇う動機付けは、派閥があったりすると、その内容自体ではなくて特定の人物の社内の意見には当然反対派もいるわけです。そしてそれが原因で社内不和を助長するケースを避けるために、結果的な方針のお墨付きというか論理的な背景を強化する面と、外圧というか外部の意見であれば、仮に結果が思わしくなくても社内での責任の所在が曖昧になるという理由もあるようですね。」
たしかこんな感じの内容でした。
人間って組織や集団になると面倒なことが多いですね。つまらないことにエネルギーを使ってるような気もします。でも日本は、和をもって尊しとするらしいので…みんなで死ねば怖くないですかね?
Posted by 木原 昌彦 at
03:24
│Comments(0)
2016年04月14日
パソコンフェチではないですよ。

初めてパソコンというものを触ったのは小学生の高学年でした。友人のお父さんがコンピュータ関連の仕事をされていたようで、ご自宅にたしかSHARPのMZシリーズ(CPUはザイログ社のZ80?)が置いてありました。グリーンディスプレイで、記憶媒体はカセットテープでした。友人と一緒にガンダムのゲームに熱中した記憶があります。それでパソコンが欲しくてたまらなかったのですが、当時は両親ともゲームするだけの機械に何十万円も払うつもりはないという考えのようでした。
中学の時にピアノを習っていて、高校生になったら帰宅部になってピアノの練習をしようと思っていましたが、当時は部活に入らない生徒は、抽選で強制的に応援団に入団させられるという制度があったため、なんとか楽な部活を探して、活動が週一回の物理部に入りました。2年生はおらず、3年生もすぐに受験で引退され、部員は私一人だっため、1年生でいきなり部長になりました。部にはNECのPC-8801markⅡSRというパソコンが使える環境がありました。これは、一世を風靡したYAMAHAのDX-7というシンセサイザーと同じFM音源(でも廉価版)を搭載しており、BASICのプログラムで音楽が鳴らせるというものでした。パソコンに詳しく音楽好きなクラスメートがいたので、部に入ってもらいいろいろ教えてもらいました。結局、物理部とは名ばかりで実際は、クラスメート5名くらいでバンド活動を始めました。でも音は波動であり、物理学の対象であるというのが言い訳でした。
大学生になって初めて自分のパソコンを買いました。NECの白黒のノートパソコンで当時25万円くらいだったかと記憶しています。大学の教養課程でパソコンの授業を履修し、ワープロの一太郎や表計算のLotus1-2-3などを覚えたり、NIfty-Serveというパソコン通信をしたり、当時アニメで人気化していた銀河英雄伝説を題材にした戦略シュミレーションなどをやってましたが、周りにはパソコン使う友人はあまりおらず、奇異な目で見られました。就職活動の時期になって急にパソコン教えてくれと手のひら返したような知人(友人ではなく)も多かったですが、基本的に無視しました。ところで、その後、WIndowsが登場してMicrosoftのOFFICEが台頭したため、せっかく覚えたLotusのマクロなどは無駄になって残念でした。ちなみにWindowシステムはMacが元祖ではなく、実はゼロックスのパロアルト研究所で研究員のために作られたシステムが起源らしいです。ビル・ゲイツや亡きジョブスなどが見学にきたそうで、新しもの好きなAppleはすぐに商品化しましたが、MicrosoftはビジネスのためにMS-DOSの互換性を優先し、10年後くらいに商品化した模様です。また、internetは軍事用の分散コンピューティングの走りであったArpanetを民間向けに転用したものです。
その後30歳くらいまでは、いわゆる3DのPCゲーマーでした。自作PCで半年ごとにビデオカードを新調していたので結構お金がかかりました。特に戦闘のリアルタイムシュミレーションなどにはまっており、OperationFlashPointというタイトルのゲームでNATOの小隊長やソ連の将校、レジスタンスのリーダーなどを深夜までやっていましたが、ある時、無理なオーバークロックでCPUを焼いてしまい、パソコン熱は一挙に冷めました。
冗長な文章を書いてしまいましたが、ある時パソコン音痴の上司とこんな会話をしました。
上司 「おい!俺のパソコンがまたおかしくなったぞ!なんとかしてくれ」
私 「またですか?まあパソコンはそういうものですよ。それでどんな症状ですか?」
上司 「何を捺しても掛け算マーク(✽:アスタリスク)が出てくるんだよ。」
私 「それは変ですね。でも、もしかしてパスワード打ってるのではないですよね。」
上司 「そうだよ!」
私 「…」
この上司は企業調査部長という肩書きでいわゆるアナリスト部門の責任者でした。こんなパソコン音痴のかたでも感心させられたことがあります。真面目にパソコンを勉強しようと自宅用に初めてパソコンを買われたのですが、こんなことを言われました。「やっとパソコン買ったぞ!でも、こんな俺でもパソコンを買ったということは、インターネット相場はそろそろ終わるんじゃないかな?」
そのとおりになりました。
Posted by 木原 昌彦 at
23:42
│Comments(0)
2016年04月14日
自分のことは棚に上げて?

最近は、比較的猫をかぶって大人しくしていますが、以前は言いたいこと言い放題でした。
たまに「何様のつもりだ!」とか「生意気な!」、「偉そうに!」、「自分のことは棚に上げて!」といった、論理的にはまったく機能していない反論(正しくは反応?)を受けたことがあります。こういう発言するかたは、おそらく思考停止しているものと認識しています。
まあ、最後の「自分のことは棚に上げて」と言うのは、世間一般では比較的通用しているような気もしますが、よく考えるとその背景にあるのは、「何を言っているのかよりも誰が言っているのかということのほうが重要」ということです。
内容が事実であったり、真実であれば、誰が言おうと関係ないのではと個人的には思っていますが、都合の悪い話をする人を黙らせるための常套句なのかなとも思います。たまにこれを言われたときは、ちょっと茶化して「とんでもない!自分のことを棚に上げているだけではなくて、棚の戸も閉めて南京錠をかけていますよ」と答えることもあります。そうすると相手は逆上して頭に血が上り、冷静な思考ができす、よりいっそうの暴言を吐いたりしますので、そこにカウンターを食らわせるということが可能ではあります。言ったことはないですが、「はい!上げてますよ。神棚に」という返しもあるかもしれません(効果はあるかな?)。
私はキリスト教(後に異端視された原始キリスト教は除く)は基本的にインチキだとは思っているのですが、高校生の時に少しだけ研究したことがありました。聖書によると、ある罪を犯した女性が石を投げられて殺されそうになった場面に遭遇したイエスが「この中で何の罪も犯していない物だけが石を投げる権利があるのでは?」というような内容を言ったというエピソードがありました。そう!ほとんどの人は何か言おうとすると結果的に「自分のことを棚にあげている」ことになりかねません。
本来は誰が言おうと、「(論理的に?)正しいことは正しく、間違っていることは間違っている」のですが、どうも世間ではそうでもないようです。
大学生の時に、とある事件のニュースを見ました。日本の女子大生グループが、イタリア旅行をして現地の日本語が流暢なイタリア人に言葉巧みに誘拐、拉致監禁され、レイプされたという事件でした。犯人のイタリア人の名前はたしか「カバキ」というのだったと思います。女子大生グループのうちの一人だけがレイプを免れたのですが、彼が逮捕された時に「なぜ、あの娘だけはレイプしなかったのか?」との質問に対し、不遜(?)にも「俺だって好みはある」と答えたそうです。この答えにはお怒りの意見が多数あったような気がしますが、私は彼の発言自体は別に間違っていないのではと思いました。怒りの対象の論点がちょっとずれているような気がしました。ちなみに傷心(傷身?)の女子大学生グループは解放されたあとに、すぐには帰国せず、旅行の続きをしたと聞いています。なんとたくましい!センチメンタル・ジャーニー?それは感傷ですね。
私は基本的な考え方として、権威主義ではありません。なぜなら権威あるかたが必ずしも正しいとは限らず、10年もすれば間違っていたことに周囲が気づくケースもままあるからです。健全なる批判精神もしくは懐疑主義は必要かと愚考します。
Posted by 木原 昌彦 at
19:17
│Comments(0)