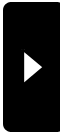2016年04月25日
君主論…現代に通用するかな?

昨夜、眠れなかったので、学生時代に原作を全巻読み、アニメも全シリーズ観た、田中芳樹氏の「銀河英雄伝説」というアニメを再度観ました。登場人物に、主人公を補佐(?)する、冷徹なる義眼こと、オーベルシュタインという参謀役がいます。彼はいわゆるマキャベリストですが、それで思い出したので以下の投稿をします。
ニコロ・マキャベッリという人物が15~16世紀のイタリアのフィレンツェにいました。フィレンツェ生まれのフィレンツェ育ちだったそうです。世界史の教科書ではマキャベリズムという名称で知られていますね。現実主義とか、目的のためなら手段を選ばないといったような、あまりいい意味では使われていません。父親は弁護士だったようですが、本人は役人で、現在の日本で言えば、外務省勤務の国家2種…つまりキャリアではなくて現場の実務家だったようです。当時、役人のトップクラスは貴族階級がなっていました。彼は貴族階級ではなく、当時通常は役人に求められていた、大学も出ていないかったにもかかわらず例外的に、実務能力を買われ、外国との交渉などで活躍していたそうです。しかし、上役が失脚したことに連座して、働き盛りの年齢で故郷のフィレンツェから追放され、郊外の山荘で執筆活動をしながら余生を送ったようです。
彼の代表作はタイトルにもある「君主論」です。当時、イタリアは統一されておらず、君主国と共和国が乱立していました。フィレンツェは形式上は共和制でしたが、事実上メディチ家が擬似君主として牛耳っていました。私は高校生の時に塩野七生女史(学習院大学史学科卒でイタリア在住の作家、代表作はローマ人の物語シリーズ)の「チェーザレ・ボルジア…あるいは優雅なる冷酷」という歴史小説を読みましたが、ニコロ・マキャベッリも登場していたので彼に興味を持ち、「君主論」や「戦術論」も読みました。もっとも、共感できない部分はあるものの、合理主義という点や当時の情勢からは当然の内容であったかと思われました。君主論では、君主国を維持するための外交や内政の方法論について述べられておりますが、詳しい内容はネタバレになるので割愛します。
実は7年前にイタリアを旅行して、フィレンツェにも行きました。ホテルの人に「マキャベッリの山荘に行きたい」と伝え、最寄駅を教えてもらい、その駅のキヨスクの女性にイタリア語わからないのに、「マキャベリ!マキャベリ!」と伝えたら、その女性の知り合いの男性が自家用車で連れて行ってくれました。山荘は現在はレストランに改装されていました。帰りはバスのストライキにあって往生しましたが、なんとか頑張ってフィレンツェ市内に戻れました。
本日も特に落ちはございませんが、まあ現代のマキャベリストはホリエモンとかかな?別に否定しているつもりはございませんが。
2016年04月24日
聖なる予言
予言と預言という言葉がありますね。前者は予め言うことですね。後者は預かった言葉という意味ですが、通常は神から預かったという設定になっています。本日の投稿のタイトルの場合は、前者のほうですが、とある本のタイトルです。
20代の頃、なせかこの本を手に取り、読みました。いわゆるスピリチャル系です。どちらかというと私は決定論者かつ唯物史観があり、この手の本は苦手でした。昔、スピリチャル系の不思議ちゃんの女性と知り合ったことがあり、会話が成り立たなくて苦労しました。論理が全く通用しなかったからです。もっとも、たいていの女性には論理は通用しませんが…。
決定論者ということで運命というものが存在するような気もします。しかし、事前には、運命の中身はわからないので実務的には存在しないのと変わりません。全ての事象が物理現象であるということであれば、人間に自由意思というものはないのかもしれません。もっとも、共産主義者ではありません。理屈としては理解できますが、まだまだ人類には高級な概念かと思われます。もちろん民主主義も同様ですが。
話を戻すと、この本は当時ベストセラーになっていて、たしか3部作くらいに続きがあり、読んでも内容がよくわからない人向けに解説書も出ていたほどです。
内容の詳細はネタバレを避けるため、割愛しますが、なかなかよく出来たストーリーでした。人類の認識や思想の進化という点では、ある程度共感ができました。人が争う原因とか、共通認識など、哲学者ユングの共時性に通ずるものもありました。もっとも、後半部分はぶっ飛んでいたのですが、まあ科学的に完全に否定できるというものでもなかったです。人類の思想はどこまで進化するのでしょうか?もちろん、進化の前に滅亡する可能性も否定はできませんね。
ちなみに私はハードカバーを購入しました。既に文庫化され、おそらくブックオフでは100円で買えるかと思いますが、念のため楽天BOOKSのリンクを貼っておきます。
20代の頃、なせかこの本を手に取り、読みました。いわゆるスピリチャル系です。どちらかというと私は決定論者かつ唯物史観があり、この手の本は苦手でした。昔、スピリチャル系の不思議ちゃんの女性と知り合ったことがあり、会話が成り立たなくて苦労しました。論理が全く通用しなかったからです。もっとも、たいていの女性には論理は通用しませんが…。
決定論者ということで運命というものが存在するような気もします。しかし、事前には、運命の中身はわからないので実務的には存在しないのと変わりません。全ての事象が物理現象であるということであれば、人間に自由意思というものはないのかもしれません。もっとも、共産主義者ではありません。理屈としては理解できますが、まだまだ人類には高級な概念かと思われます。もちろん民主主義も同様ですが。
話を戻すと、この本は当時ベストセラーになっていて、たしか3部作くらいに続きがあり、読んでも内容がよくわからない人向けに解説書も出ていたほどです。
内容の詳細はネタバレを避けるため、割愛しますが、なかなかよく出来たストーリーでした。人類の認識や思想の進化という点では、ある程度共感ができました。人が争う原因とか、共通認識など、哲学者ユングの共時性に通ずるものもありました。もっとも、後半部分はぶっ飛んでいたのですが、まあ科学的に完全に否定できるというものでもなかったです。人類の思想はどこまで進化するのでしょうか?もちろん、進化の前に滅亡する可能性も否定はできませんね。
ちなみに私はハードカバーを購入しました。既に文庫化され、おそらくブックオフでは100円で買えるかと思いますが、念のため楽天BOOKSのリンクを貼っておきます。
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】聖なる予言 [ ジェームズ・レッドフィールド ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0426%2f04269301.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0426%2f04269301.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】聖なる予言 [ ジェームズ・レッドフィールド ] |
2016年04月24日
善と悪?
若い頃は白黒はっきりさせたいほうで、特に仕事では上司や経営者とよく喧嘩していました。今でも基本的な考え方はそうで、多くのケースでは白黒は脳内ではつけますが、話をする相手を事前にプロファイリングして、前提条件や論理プロセスを共有できない相手だとトラブルにしかならないので、その場合は思ったことはなるべく言わないようにしています。
白黒というとデジタル的ですが、二元論というのは私が知っている限りでは拝火教、つまりゾロアスター教に遡れるようで、キリスト教にも影響があったようです。善と悪、神と悪魔のということのようですね。
最近、国内外で日本の安全保障関連法案に対し、様々な意見があり、不毛な(?)議論が続いているようです。日本は一応、民主主義ということになっており、民主主義は多数決を基本にしています。もちろん多数意見が必ずしも正しいとは思っていませんが、一応ルールということでは尊重する姿勢でいます。
人間はこれまで様々な概念や思想を生み出しました。しかし、思想が醸成されるには多くの場合(純粋な哲学や科学思想は別にして)、経済環境に影響を受けると考えています。
私は何か思いついた時にその論理的なプロセスは別にして、なぜそう思うに至ったのかといった自分の周辺の状況を考慮するようにしていますが、演繹的な論理展開ではない部分は、そう思わせる何かが存在するような気もします。いわゆる気のせいです。
突き詰めると善と悪は所詮、立場の異なる大人の事情だったり、都合だったりしますが、最適化目的の事前設定がなければ、議論は空転し、単なる異なった目的(もしくは利害関係?)による討論になりかねませんね。事実は一つしかなくても真実は人によって異なるようです。
うーん…しばらく資産運用関係の投稿ばかりしていたので、たまには柔らかいことを書こうと思いましたが…なんとなくクリスタルではなく観念論…しかし、グレーゾーンというのは現実では広範囲な気がします…
白黒というとデジタル的ですが、二元論というのは私が知っている限りでは拝火教、つまりゾロアスター教に遡れるようで、キリスト教にも影響があったようです。善と悪、神と悪魔のということのようですね。
最近、国内外で日本の安全保障関連法案に対し、様々な意見があり、不毛な(?)議論が続いているようです。日本は一応、民主主義ということになっており、民主主義は多数決を基本にしています。もちろん多数意見が必ずしも正しいとは思っていませんが、一応ルールということでは尊重する姿勢でいます。
人間はこれまで様々な概念や思想を生み出しました。しかし、思想が醸成されるには多くの場合(純粋な哲学や科学思想は別にして)、経済環境に影響を受けると考えています。
私は何か思いついた時にその論理的なプロセスは別にして、なぜそう思うに至ったのかといった自分の周辺の状況を考慮するようにしていますが、演繹的な論理展開ではない部分は、そう思わせる何かが存在するような気もします。いわゆる気のせいです。
突き詰めると善と悪は所詮、立場の異なる大人の事情だったり、都合だったりしますが、最適化目的の事前設定がなければ、議論は空転し、単なる異なった目的(もしくは利害関係?)による討論になりかねませんね。事実は一つしかなくても真実は人によって異なるようです。
うーん…しばらく資産運用関係の投稿ばかりしていたので、たまには柔らかいことを書こうと思いましたが…なんとなくクリスタルではなく観念論…しかし、グレーゾーンというのは現実では広範囲な気がします…
Posted by 木原 昌彦 at
17:01
│Comments(0)
2016年04月24日
ウソつきは政治家のはじまり?

私は基本、新聞を読むのも、テレビを観るのもずいぶん前に卒業しました。読んだり、観たりすると内容のみならず表現方法の間違いが気になるからです。
若い頃、企業調査や経済調査の仕事をしていました。調査の前には、対象に関する記事などを収集してから、取材先に裏をとったりもしました。結果として間違いであった記事が散見されました。もっとも、新聞記事やテレビのニュースの内容が本当だと思っている人は最近はあまりいないのではとも想像します。結論としては、世の中を主成分分析した場合、ウソとインチキが大半を占めているのではないかと思っています。
最近、政治家がウソを言ったとかなんとかで話題になっているとひとから聞きます。
以前もブログで書いたことがありますが、私は民主制とか民主政には懐疑的です。
世の中いろんな考え方がありますが、まあいろんな人の意見を聞いていたら収拾がつかないかとも思います。
政治家が何かを成し遂げるために、詭弁を弄したり、有権者を騙すのは昔からあることですが、なぜそんに露骨なのだろうかとも思います。
先日、とあるセミナーで講師の方から聞いたのですが、「中国の政治家は、人民が7億人死んでも、残り3億が残ったら大丈夫と言っている」とのことです。ある意味、おおらかな考えかたとも言えます。さすが4千年の歴史がありますね。
ユダヤ人はかつて国が滅んだけれども、放浪しながらも自身の文化を(ある程度)後世に伝え、国を再興しました。日本人も一度、国土を失ってみるという経験が必要なのかとも思います。
政治家のウソを好意的に取ると、「敵を欺くにはまず味方から」か「嘘から出たマコト」でしょうか。
今日もとりとめもなく書いてしまいました。まあ、兼好法師の徒然草のような設定で。
おまけです。嘘つきが言った「私は嘘つきです」…本当に嘘つきなのかな?
2016年04月24日
保険をぐるりと?
一時期、昔ながらの「ニッセイのおばちゃん」や「ニッセイレディ」などのスタイルの保険の外交員は絶滅の危機にあったようですが、最近は回復しているようです。動物の絶滅危惧種は保護されたりもしますが、本来、動物の絶滅の原因の多くは人間のせいでもあります。しかし職種となると、要は世の中に必要とされないからということで、一部の例外を除き、保護する必要はないかと思われます。戦前は、男性の専門的(?)外交員が販売していましたが、大東亜戦争で戦争寡婦が溢れ、彼女たちに何か仕事を与えなければということで政府が様々な業界に打診したところ、日本生命が手を上げたと聞いています。要は、主婦を顧客ターゲットとして、戦争寡婦の販売員に「私の主人は戦争で亡くなったので、今は大変な思いをしています。あなたはご主人が生きておられて幸せですね。でも、いつ私のような目にあうかもわかりませんよ」といった、同情と危機感を煽るセールストークだった模様です。
かつてのスタイルが通用しなくなってきたのは、いわゆる外資系保険会社スタイル(ライフプランニング)や多くの保険会社の商品を扱う店舗型やFP事務所が注目されていることと、銀行が投資信託と同様に保険商品を扱っていることが影響しているのではと思われます。保険商品の中身や営業の方の様々な情報やサポートというより、単に付き合いで加入するケースもあるでしょうが、世の中だんだん厳しくなると、(当たり前ですが)サービスの質を問われるという方向に向かっているのかもしれません。
これまで多くの保険外交員のかたとはやりとりをしていますが、なかには面白いエピソードがあります。
倒産して外資系に買われたかつてのT生命という会社の女性外交員は強烈でした。
私が新入社員だったころ、昼休みに研修先まで押しかけてきて、「あなたの先輩はみんな私から保険を契約したのよ」と意味不明なことを言ってきました。それで「それが、どうかしたのですか?」と答え、この時点で、この人から契約するのは絶対にやめておこうと思いました。その後、同期の男性から飲み会に誘われて行ってみたら、実はこのT保険のかたが企画した合コンでした。保険会社に入社したばかりの女子社員との合コンで、なんだか嫌な予感がしたので私は1次会で帰りました。2次会に参加し人から聞いた話では、2次会では保険の契約を勧められ、同期の一人はその場で契約しました。そしてその保険会社の新入社員の女性と結婚したと聞いています。
その後、T生命が倒産し、保険契約の一部が目減りするような事態になった時、安易に契約するべきではないなあと思いました。その女性外交員はしばらく顔を見せませんでしたが、ほとぼりがさめたのか、外資系により会社が新しくなったらまた顔を出すようになりました。女性は強いなあと思いました。
30代半ばの頃、会社のオフィスを訪ねてきた、中年の女性外交員がいました。新しく担当になったとのことで、挨拶にこられたついでに、当時興味を持っていた保険商品について聞きたかったので、内容の条件を伝え、後日提案書をもってきてもらいました。たしか、税制とその商品との関連性について質問したら、「そういうことはわかりません」との回答だったので驚き、なぜ保険会社に入ったのか聞いてみたら、「実は最近離婚して、アルバイトしてたのですが、それだけでは生活が苦しいので知り合いに相談したら保険を売る仕事を勧められて…」と言われました。特に同情はしませんでしたが、私の質問については調べてもらうということになりました。翌日くらいには連絡があるものかと思っていたら、1週間以上放置されたので、こちらから名刺にあった電話番号に連絡したら、当人は辞めてしまったとのことでした。
知人から聞いた話では、保険の契約を取るために、いわゆる枕営業する女性も結構いたとのことですが、なかなか厳しい世の中です。でも、生きていけるだけでも良いのかもしれません。大学生の就職が厳しかったころ、風俗業界に流れる女子学生も多かったようです。
私は一時期、ソニー生命というところでアルバイトした時と、地元で銀行員やっていた時に、多少保険の勉強した関係で、現在契約している保険は、自分で内容を調べたものと、外資系の男性外交員から教えてもらって契約したものです。でも、最近は、信頼できるかたに一元管理してもらったほうがいいような気もします。
かつてのスタイルが通用しなくなってきたのは、いわゆる外資系保険会社スタイル(ライフプランニング)や多くの保険会社の商品を扱う店舗型やFP事務所が注目されていることと、銀行が投資信託と同様に保険商品を扱っていることが影響しているのではと思われます。保険商品の中身や営業の方の様々な情報やサポートというより、単に付き合いで加入するケースもあるでしょうが、世の中だんだん厳しくなると、(当たり前ですが)サービスの質を問われるという方向に向かっているのかもしれません。
これまで多くの保険外交員のかたとはやりとりをしていますが、なかには面白いエピソードがあります。
倒産して外資系に買われたかつてのT生命という会社の女性外交員は強烈でした。
私が新入社員だったころ、昼休みに研修先まで押しかけてきて、「あなたの先輩はみんな私から保険を契約したのよ」と意味不明なことを言ってきました。それで「それが、どうかしたのですか?」と答え、この時点で、この人から契約するのは絶対にやめておこうと思いました。その後、同期の男性から飲み会に誘われて行ってみたら、実はこのT保険のかたが企画した合コンでした。保険会社に入社したばかりの女子社員との合コンで、なんだか嫌な予感がしたので私は1次会で帰りました。2次会に参加し人から聞いた話では、2次会では保険の契約を勧められ、同期の一人はその場で契約しました。そしてその保険会社の新入社員の女性と結婚したと聞いています。
その後、T生命が倒産し、保険契約の一部が目減りするような事態になった時、安易に契約するべきではないなあと思いました。その女性外交員はしばらく顔を見せませんでしたが、ほとぼりがさめたのか、外資系により会社が新しくなったらまた顔を出すようになりました。女性は強いなあと思いました。
30代半ばの頃、会社のオフィスを訪ねてきた、中年の女性外交員がいました。新しく担当になったとのことで、挨拶にこられたついでに、当時興味を持っていた保険商品について聞きたかったので、内容の条件を伝え、後日提案書をもってきてもらいました。たしか、税制とその商品との関連性について質問したら、「そういうことはわかりません」との回答だったので驚き、なぜ保険会社に入ったのか聞いてみたら、「実は最近離婚して、アルバイトしてたのですが、それだけでは生活が苦しいので知り合いに相談したら保険を売る仕事を勧められて…」と言われました。特に同情はしませんでしたが、私の質問については調べてもらうということになりました。翌日くらいには連絡があるものかと思っていたら、1週間以上放置されたので、こちらから名刺にあった電話番号に連絡したら、当人は辞めてしまったとのことでした。
知人から聞いた話では、保険の契約を取るために、いわゆる枕営業する女性も結構いたとのことですが、なかなか厳しい世の中です。でも、生きていけるだけでも良いのかもしれません。大学生の就職が厳しかったころ、風俗業界に流れる女子学生も多かったようです。
私は一時期、ソニー生命というところでアルバイトした時と、地元で銀行員やっていた時に、多少保険の勉強した関係で、現在契約している保険は、自分で内容を調べたものと、外資系の男性外交員から教えてもらって契約したものです。でも、最近は、信頼できるかたに一元管理してもらったほうがいいような気もします。
Posted by 木原 昌彦 at
11:53
│Comments(0)
2016年04月24日
インフォメーション・レシオ(情報比)
先日、運用のスタイルということについて投稿しました(URLは以下の通り)。
http://schole.chesuto.jp/e1381470.html
アクティブ運用とパッシブ運用という分類があるということを書いています。おおまかに言えば、ベンチマークとするインデックスに勝つことを目的としているのをアクティブと考えて良いかと思います。
インデックスに勝つための哲学としては市場は非効率であるという前提があり、まあ否定できない点も多くあるかと思います。しかし、非効率であるということを前提としたとしていても、その非効率部分を発見する方法論が必要です。可能であれば、安定的に発見できればいいのですが、コスト面などで不利なこともあり、なかなか困難な場合が多いです。
一般的には、投資家の多くは結果にしか興味を持たないようです。いわゆる勝てば官軍であって、勝った理由とかプロセスはどうでも良いということですね。もっとも、それは価値観の問題なので特に否定はしません。
ファンドのパフォーマンス評価の仕事をしていた時は、もちろん単純に勝ったか負けたかという結果だけ注目する訳には業務上いきませんでした。ファンド評価によく使われるのにシャープ・レシオというのがあり、こちらは以前ブログに書いたことがあります。(以下URL)
http://schole.chesuto.jp/e1377361.html
しかし、アクティブなファンドを評価する場合は、インフォメーション・レシオ(情報比)という指標があり、計算方法としては、超過収益率の平均値をアクティブリスク(超過収益の標準偏差、リスクモデルによる事前推定値を使用する場合もあります)で除するというものです。つまり、テイクしたアクティブリスクに対してどれだけの超過収益があったかということです。過大なリスクを取っていれば、たまに驚異的なリターンを獲得することがあります。しかし、それは当たり前のことであって運用能力があるとは必ずしも言えないケースがままあります。
また、シャープレシオの場合は絶対的な数値自体にはあまり意味がないということを書きましたが、インフォメーションレシオの場合はそれなりに意味を有し、この数値が0.5~1.0程度あるとそこそこうまくいっており、2.0以上となるケースは非常に稀で相当に良い成績と言われます。私はファンドの評価業務において、(頼まれもしないのに)超過収益率のt検定なども行っていました。それによると多くのケースだとうまくいっているのは、ほぼ偶然の範囲内でした。しかし、一方で統計的に有意な水準で超過収益率を出しているものは、かなりの少数派でしたが存在はしていたと記憶しています。
王貞治さんと長嶋茂雄さんを比較して「記録よりも記憶」という表現がありますが、厳密な統計的事実よりも曖昧な印象の方がひとを満足させることなのかもしれません。そもそも個人の投資家の場合、通常は(可能かどうかは別にして)絶対的なリターン獲得が目的であり、インデックスに勝つことを目標にしているのは少数派だと思います。私見ですが、よくわからない時は何もしない、つまり「休むも相場」ということを選択するのも重要かもしれませんね。自信や確信が持てる時だけ投資行動を行う、ヒット&アウェイのほうが良いかもしれません。
http://schole.chesuto.jp/e1381470.html
アクティブ運用とパッシブ運用という分類があるということを書いています。おおまかに言えば、ベンチマークとするインデックスに勝つことを目的としているのをアクティブと考えて良いかと思います。
インデックスに勝つための哲学としては市場は非効率であるという前提があり、まあ否定できない点も多くあるかと思います。しかし、非効率であるということを前提としたとしていても、その非効率部分を発見する方法論が必要です。可能であれば、安定的に発見できればいいのですが、コスト面などで不利なこともあり、なかなか困難な場合が多いです。
一般的には、投資家の多くは結果にしか興味を持たないようです。いわゆる勝てば官軍であって、勝った理由とかプロセスはどうでも良いということですね。もっとも、それは価値観の問題なので特に否定はしません。
ファンドのパフォーマンス評価の仕事をしていた時は、もちろん単純に勝ったか負けたかという結果だけ注目する訳には業務上いきませんでした。ファンド評価によく使われるのにシャープ・レシオというのがあり、こちらは以前ブログに書いたことがあります。(以下URL)
http://schole.chesuto.jp/e1377361.html
しかし、アクティブなファンドを評価する場合は、インフォメーション・レシオ(情報比)という指標があり、計算方法としては、超過収益率の平均値をアクティブリスク(超過収益の標準偏差、リスクモデルによる事前推定値を使用する場合もあります)で除するというものです。つまり、テイクしたアクティブリスクに対してどれだけの超過収益があったかということです。過大なリスクを取っていれば、たまに驚異的なリターンを獲得することがあります。しかし、それは当たり前のことであって運用能力があるとは必ずしも言えないケースがままあります。
また、シャープレシオの場合は絶対的な数値自体にはあまり意味がないということを書きましたが、インフォメーションレシオの場合はそれなりに意味を有し、この数値が0.5~1.0程度あるとそこそこうまくいっており、2.0以上となるケースは非常に稀で相当に良い成績と言われます。私はファンドの評価業務において、(頼まれもしないのに)超過収益率のt検定なども行っていました。それによると多くのケースだとうまくいっているのは、ほぼ偶然の範囲内でした。しかし、一方で統計的に有意な水準で超過収益率を出しているものは、かなりの少数派でしたが存在はしていたと記憶しています。
王貞治さんと長嶋茂雄さんを比較して「記録よりも記憶」という表現がありますが、厳密な統計的事実よりも曖昧な印象の方がひとを満足させることなのかもしれません。そもそも個人の投資家の場合、通常は(可能かどうかは別にして)絶対的なリターン獲得が目的であり、インデックスに勝つことを目標にしているのは少数派だと思います。私見ですが、よくわからない時は何もしない、つまり「休むも相場」ということを選択するのも重要かもしれませんね。自信や確信が持てる時だけ投資行動を行う、ヒット&アウェイのほうが良いかもしれません。
2016年04月24日
部品が多いと?
記憶が曖昧ですが、たしか高校生の時の先生に教えられたような気がします。
「部品が多いと故障の可能性が高まる」ということです。
構造が単純であると、故障はし難いですが、精密機械はちょっとしたことで機能不全に陥ることがあります。卑近な例で言えば、ハンマーとコンピュータでしょうか?ハンマーが故障というか使い物にならなくなるのはよっぽどのことだと思いますが、コンピュータは多くの機能を有するために構造が複雑で、ちょっとしたソフトウェアのバグやサイバー攻撃でダウンしたりします。
世の中は複雑であると思っていはいますが、あまりあれこれ考えると、脳が機能不全になるのではないかという気がしています。たぶん物事を単純に考え、喜怒哀楽を素直に表現する方が幸せなんだろうとも思います。
認識する対象が複雑なのか、それとも認知する意識が複雑なのかははっきりとはわかりません。しかし、複雑な事象も、単純な認知においては単純に見えるため、やはり意識の問題のような気がします。
アナリストという仕事をしていた時、当時の上司に言われました。
「株が上がるとか下がるとか、そんな瑣末なことに一喜一憂するなんて馬鹿げてると思わないか?ほかに有意義なことがいくらでもあると思うぞ。有意義なことに時間を使わないとな」
当時も今でも私は同意見です。そしてこの話のあと、私は転職(転社?)しましたが、半年後にその上司はガンで亡くなられました。そのかたは一体何がしたかったのかはわかりませんが、無念であったろうとは思います。
それなりに有効な投資手法は、専門的で複雑怪奇なところがあります。人にその内容を伝えるのは簡単ではなく、段階をおいて説明する必要があったりしますが、そういうことに興味を持たれなければ、全く意味をなしません。しかし、小難しいことを考えずに、不合理であっても、単純に考えて単純な投資で一喜一憂するほうが、もしかしたら当人は幸せなのかもしれません。
まあ、人は投資するために生きている訳では、たぶんないので…では何のために生きているのでしょうか?
うーん…当初の予定からは全く異なる、脈絡のないことを書いてしまいました…疲れているのかな?こころが故障しているのかな?セロトニン不足かも…?
「部品が多いと故障の可能性が高まる」ということです。
構造が単純であると、故障はし難いですが、精密機械はちょっとしたことで機能不全に陥ることがあります。卑近な例で言えば、ハンマーとコンピュータでしょうか?ハンマーが故障というか使い物にならなくなるのはよっぽどのことだと思いますが、コンピュータは多くの機能を有するために構造が複雑で、ちょっとしたソフトウェアのバグやサイバー攻撃でダウンしたりします。
世の中は複雑であると思っていはいますが、あまりあれこれ考えると、脳が機能不全になるのではないかという気がしています。たぶん物事を単純に考え、喜怒哀楽を素直に表現する方が幸せなんだろうとも思います。
認識する対象が複雑なのか、それとも認知する意識が複雑なのかははっきりとはわかりません。しかし、複雑な事象も、単純な認知においては単純に見えるため、やはり意識の問題のような気がします。
アナリストという仕事をしていた時、当時の上司に言われました。
「株が上がるとか下がるとか、そんな瑣末なことに一喜一憂するなんて馬鹿げてると思わないか?ほかに有意義なことがいくらでもあると思うぞ。有意義なことに時間を使わないとな」
当時も今でも私は同意見です。そしてこの話のあと、私は転職(転社?)しましたが、半年後にその上司はガンで亡くなられました。そのかたは一体何がしたかったのかはわかりませんが、無念であったろうとは思います。
それなりに有効な投資手法は、専門的で複雑怪奇なところがあります。人にその内容を伝えるのは簡単ではなく、段階をおいて説明する必要があったりしますが、そういうことに興味を持たれなければ、全く意味をなしません。しかし、小難しいことを考えずに、不合理であっても、単純に考えて単純な投資で一喜一憂するほうが、もしかしたら当人は幸せなのかもしれません。
まあ、人は投資するために生きている訳では、たぶんないので…では何のために生きているのでしょうか?
うーん…当初の予定からは全く異なる、脈絡のないことを書いてしまいました…疲れているのかな?こころが故障しているのかな?セロトニン不足かも…?
Posted by 木原 昌彦 at
05:58
│Comments(0)
2016年04月24日
運用プロセスとディスクロージャー
昔取った杵柄で、知人の保有している投資信託の分析をすることがあります。定量分析は当然ですが、より重視しているのは定性面で、運用会社の哲学や姿勢、リソース、ファンドの運用プロセスなどです。具体的には、販売用資料や、目論見書(何か目論んでいる?)、週次、月次の報告書などをチェックします。実は、運用会社に在籍していた時にどれも実際に作成していた経験があります。
購入者にとっては、なんでもいいから儲かればいいと思うのは当然かもしれません。しかし、儲かるというのは偶然の要素が多いというか、確率論ので世界でもあります。以前、ご紹介した本の「まぐれ」の副題のように「投資家は運を実力と勘違いする」ケースもままあります。なので少なくともご自分の投資行動がいったい何を意味しているのかぐらいは知っておたほうが良いと考えていますし、知り合いにはそう伝えています。しかし、そういったことに興味がなく、何を買えばいいのかという結論だけを知りたいというかたも多いようです。
話がそれましたが、定性分析の中でも、哲学はまたの機会にするとして、通常はファンドの運用プロセスというものがあります。具体的には運用の目的(安定的な信託財産の成長という曖昧な表現も多いです。)で超過収益を獲得するのかとか、絶対収益を獲得するなどがあり、そしてその目的をどのような手段で実現するかということが書かれています。そのプロセスにそれなりに合理性があり、それを実現するためのリソースがその会社にあるようであれば、一応納得はします。
ここ数年で設定されたファンドで散見されるのは、いわゆる安定的な毎月分配金を出すために(?)、通常のオーソドックスな運用以外に、ちょっと欲張ってプラスアルファを出す仕組みを設けていることがあります。オプションや先物、通貨の取引を使った追加的な収益の獲得を目指しているものが多く見られました。そのこと自体は否定しません。しかし、結果的にうまくいかないケースも多くあり、出来もしない余計なことをしないほうが良いのではとも思うファンドもあります。
話は変わって、週報や月報ですが、それなにり受益者のために真面目に仕事している会社であれば、上記の運用プロセスに沿った形で、市況や投資行動の内容、そしてその結果などについて説明が書かれているべきと考えています。しかしながら人材不足なのか、手を抜いているのか、それともポジショントークを避けているのかは不明ですが、なんら説明責任を果たしていない報告書も多くあります。よくあるのは、基準価格の推移、組入上位銘柄、投資対象の市場のチャートなどを貼り付けただけのものです。私見ですが、そんな情報では、運用の成果の原因などが何なのかさっぱりわかりません。通常は運用プロセスに即した、寄与度などを計算する要因分析が抜けていたら、まずは手抜きであると思っています。真面目にやっているところもあれば、それなりの規模がある会社であっても、明らかに無意味な報告書を公表しているところもあります。
保有されているファンドの運用報告書を見られたことはありますか?読んでもなんだかわからなければ、そういう投資信託は保有しないほうが基本的には良いかと思っています。
購入者にとっては、なんでもいいから儲かればいいと思うのは当然かもしれません。しかし、儲かるというのは偶然の要素が多いというか、確率論ので世界でもあります。以前、ご紹介した本の「まぐれ」の副題のように「投資家は運を実力と勘違いする」ケースもままあります。なので少なくともご自分の投資行動がいったい何を意味しているのかぐらいは知っておたほうが良いと考えていますし、知り合いにはそう伝えています。しかし、そういったことに興味がなく、何を買えばいいのかという結論だけを知りたいというかたも多いようです。
話がそれましたが、定性分析の中でも、哲学はまたの機会にするとして、通常はファンドの運用プロセスというものがあります。具体的には運用の目的(安定的な信託財産の成長という曖昧な表現も多いです。)で超過収益を獲得するのかとか、絶対収益を獲得するなどがあり、そしてその目的をどのような手段で実現するかということが書かれています。そのプロセスにそれなりに合理性があり、それを実現するためのリソースがその会社にあるようであれば、一応納得はします。
ここ数年で設定されたファンドで散見されるのは、いわゆる安定的な毎月分配金を出すために(?)、通常のオーソドックスな運用以外に、ちょっと欲張ってプラスアルファを出す仕組みを設けていることがあります。オプションや先物、通貨の取引を使った追加的な収益の獲得を目指しているものが多く見られました。そのこと自体は否定しません。しかし、結果的にうまくいかないケースも多くあり、出来もしない余計なことをしないほうが良いのではとも思うファンドもあります。
話は変わって、週報や月報ですが、それなにり受益者のために真面目に仕事している会社であれば、上記の運用プロセスに沿った形で、市況や投資行動の内容、そしてその結果などについて説明が書かれているべきと考えています。しかしながら人材不足なのか、手を抜いているのか、それともポジショントークを避けているのかは不明ですが、なんら説明責任を果たしていない報告書も多くあります。よくあるのは、基準価格の推移、組入上位銘柄、投資対象の市場のチャートなどを貼り付けただけのものです。私見ですが、そんな情報では、運用の成果の原因などが何なのかさっぱりわかりません。通常は運用プロセスに即した、寄与度などを計算する要因分析が抜けていたら、まずは手抜きであると思っています。真面目にやっているところもあれば、それなりの規模がある会社であっても、明らかに無意味な報告書を公表しているところもあります。
保有されているファンドの運用報告書を見られたことはありますか?読んでもなんだかわからなければ、そういう投資信託は保有しないほうが基本的には良いかと思っています。
2016年04月24日
格差?
以前、出張で大分県の中津市というところに何度か行きました。唐揚げが有名だそうですね。そして中津駅前に福澤諭吉氏の像があるのを見つけ、このかたが中津藩士だったということを知りました。
同氏が創設された慶応義塾大学のサイトに、生涯の年譜があったので見てみました。URLは以下の通りです。
http://www.keio.ac.jp/ja/contents/fukuzawa_history/
なかなかご苦労されたようですね。そして幼少の頃より酒好きだったというところが面白いです。
著書「学問のすすめ」の冒頭に、「天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずといえり」というのがありますが、どうやらこれはアメリカの独立宣言を意訳したもののようです。そして続きとしては、現実には貧富の差があり、学問があるかないかで格差ができる、というような内容だったかと記憶しています。もちろん、生まれた時点で貧富の差は既にあったりしますし、学力の差が親の収入と比例関係にあるという統計もあるようです。まあ、学校のお勉強だけで人生が決まるとは思いませんが、知識がないよりはあったほうが、学力がないよりはあったほうが当然のことながら幸福になるためのアドバンテージがあるような気はします。もっとも、知らぬが仏、知らないほうが幸せということもあるかもしれません。
ところで、1万円紙幣に肖像が使われてますね。お金だけが幸福の要因ではないですが、知識という点で同様なことが言えるのかなとも思われます。税制を知らなかったために損をしたり、投資について知らなかったために、機会を逸したり、金融マンに騙されたりということです。投資は富裕層のためにあるのではないということを以前、このブログで書いたことがありますが、お金が儲かるかどうかというような問題ではなく、老後の生活を維持できるかどうかという切実な問題が近い将来、起き始めるようです。これまでは普通に(適当に?)仕事していたら、老後に問題は生じることはすくなかったでしょうが、今後は世の中の動きに無頓着であったために、生活苦に陥る可能性も高くなってきました。
福澤氏の晩年の著作「痩せ我慢の説」の冒頭に「立国は私なり。公に非ざるなり。」というのがあり、国の繁栄には国民の能力や努力が重要ということなのでしょう。政治がうまくいかないのは政治家のせいではなく国民の無知のせいという意味にもとれるようです。まあ、あまり国を当てにせずに自助努力が必要なのかと思われます。
最後におまけですが、中津駅前で撮影した福澤氏の銅像です。

同氏が創設された慶応義塾大学のサイトに、生涯の年譜があったので見てみました。URLは以下の通りです。
http://www.keio.ac.jp/ja/contents/fukuzawa_history/
なかなかご苦労されたようですね。そして幼少の頃より酒好きだったというところが面白いです。
著書「学問のすすめ」の冒頭に、「天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずといえり」というのがありますが、どうやらこれはアメリカの独立宣言を意訳したもののようです。そして続きとしては、現実には貧富の差があり、学問があるかないかで格差ができる、というような内容だったかと記憶しています。もちろん、生まれた時点で貧富の差は既にあったりしますし、学力の差が親の収入と比例関係にあるという統計もあるようです。まあ、学校のお勉強だけで人生が決まるとは思いませんが、知識がないよりはあったほうが、学力がないよりはあったほうが当然のことながら幸福になるためのアドバンテージがあるような気はします。もっとも、知らぬが仏、知らないほうが幸せということもあるかもしれません。
ところで、1万円紙幣に肖像が使われてますね。お金だけが幸福の要因ではないですが、知識という点で同様なことが言えるのかなとも思われます。税制を知らなかったために損をしたり、投資について知らなかったために、機会を逸したり、金融マンに騙されたりということです。投資は富裕層のためにあるのではないということを以前、このブログで書いたことがありますが、お金が儲かるかどうかというような問題ではなく、老後の生活を維持できるかどうかという切実な問題が近い将来、起き始めるようです。これまでは普通に(適当に?)仕事していたら、老後に問題は生じることはすくなかったでしょうが、今後は世の中の動きに無頓着であったために、生活苦に陥る可能性も高くなってきました。
福澤氏の晩年の著作「痩せ我慢の説」の冒頭に「立国は私なり。公に非ざるなり。」というのがあり、国の繁栄には国民の能力や努力が重要ということなのでしょう。政治がうまくいかないのは政治家のせいではなく国民の無知のせいという意味にもとれるようです。まあ、あまり国を当てにせずに自助努力が必要なのかと思われます。
最後におまけですが、中津駅前で撮影した福澤氏の銅像です。

Posted by 木原 昌彦 at
00:28
│Comments(0)
2016年04月23日
無知の知?無恥の恥?

中学生の時、道徳という授業がありました。なんだか一定の価値観を押し付ける洗脳みたいで正直嫌いでしたが、テキストはひととおり目を通しました。シラノ・ド・ベルジュラックの話など記憶に残っています。
でも一番共感を覚えたのはギリシゃの哲学者ソクラテスの話でした。いわゆる対話によって、物事を深く掘り下げ、より良い解決法を見つける共同作業を行うというものです。今風に言うとブレーン・ストーミング的なことなのでしょうか?
ディベートと言う言葉がありますが、討論のことですね。目的は相手を論破するゲームのようなもので虚しさも覚えます。議論すべきところが、結果的に討論になっているのは、お互いに信頼関係がないか、既に結論が決まっており、平行線であるということでしょうか。全く時間の無駄に思えます。
大事なのは誠意ある態度での対話かもしれません。自分の考えだと思っていても、実は誰かの受け売りだったりすることはままあります。マスコミの情報も信用できないことが多々ありますね。一人の人間が知っていることなどちっぽけなので、当然、勘違いや間違いもあるかと思います。でも、間違っていると気づいたら素直に認めることが大事かと思いますが、なかなか(根拠のない)プライドを持っていたりすると難しいかもしれませんね。知らないことが多すぎると知らないということ自体も知らなかったりしますが、私の少ない経験では、知ろうとするともっとわからないことが増えたりもします。
しかし、自分が対話する姿勢を示しても相手がそうだとは限りません。ソクラテスは空気が読めなかったのか、結局、刑死することになりました。言論が暴力に勝つのは希だとも思えます。私はキリスト教徒ではないので、右の頬を打たれそうになったらスウェイバックで避けて…
Posted by 木原 昌彦 at
23:08
│Comments(0)