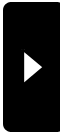2016年04月23日
茹で蛙?

先日、あるかたのfacebookの投稿で、久しぶりにタイトルの言葉を見ました。20年くらい前に初めて知りましたが、懐かしく思いました。意味合いとしては、蛙を熱湯に投げ入れると条件反射的に脱出しますが、徐々に温度を上げていくと変化に気づくのが遅れ、結果的に茹で上がって死んでしまうということです。
生まれてから、死ぬまでに社会環境にそれほど変化がなければ、予測もしやすく計画的にコツコツ努力をするひとが成功する確率も高くなるかと思います。
ここ20年くらいを振り返ると、それ以前ではありえないと思われた現象が多数起こっており、こんなはずではなかったと思われるひとも多いかとも思われます。
しかしながら、人類の過去の歴史を振り返ると、そんなことは日常茶飯事ですね。意外に安定している時期というのは短いものかとも感じます。
もちろん、普遍的なこともあるかもしれません。それは適者生存ということです。国が守ってくれるとは限りません。国というのは所詮、便宜上存在するものですので、条件が変われば存亡は危うくなりますね。
幕末の新選組を美化するケースもありますが、見方によれば、武士に憧れた武士ではないかたが、武士以上に武士らしく生きようともがいただけで、情勢を読めなかった近視眼的な悲しさも漂います。
もっとも、判官贔屓と言うように日本人は敗北者に同情するという文化があるようです。それはそれで美徳とも思われます。
変化が急激な場合、その変化についていけない人たちもいます。社会全体の安定性を保つには、そういったかたへの救済措置も必要です。しかしながらそればかりに注目していると社会全体の競争力が失われ、その社会自体が成り立たなくなることもありうるとは思いますので、バランス感覚が必要です。でも、全てのひとを救おうとするのは、現実的に難しいかとも思われます。
まあ、全員が生き残る必要はもともとないかもしれませんので、自助努力で生き残れるひとが生き残ればいいのかな?なんだかアナーキーな感じもしますが…ノアの箱舟が来てるのかも…?
Posted by 木原 昌彦 at
21:44
│Comments(0)
2016年04月23日
顧客満足?
基本的に全ての満足は自己満足であると思っています。ボランティア精神だったり、義務感、正義感、使命感といったものもあるのでしょうが、要するにそうしている自分が好きであるという自己満足なのではとも考えています。
仕事というのは通常、顧客というものが存在し、一般的には顧客満足が得られなければ成り立たなくなります。顧客の満足をどのように得るかということには、様々な方法が考えられますが、おおまかには以下の通りです。
①本業で役に立つ
②巧妙な詐欺行為を行い、顧客に勘違いをさせる
③仕事とは関係ないことで役に立つ
①はそうあれば良い理想的な状態、②は意図してか結果的にそうするケースも考えられますが詐欺が発覚した時が困ります。そして③もそれなりに有効かと思っています。分かりやすい例でいえば、釣りバカ日誌の浜ちゃんのようなスタイルのことです。
ずいぶん前ですが、山一證券という証券会社が倒産しました。実は、倒産前に東京の中央区新川に本社が移転したのですが、その近辺は倒産ストリートと一部には言われてました。当時私の会社のオフィスは隣の茅場町でした。、新川はちょっと外れにあって家賃も安いようですが、山一がこんなところに移ってくるのかと驚いたものです。
当時は、それなりにニュースで大きく取り上げられましたが、印象に残ったニュース映像がありました。山一株などを購入していた、品のある老婦人がインタビューを受けていました。そのかた曰く「たしかに株で損はしましたけど、週に数回、若い男性の営業マンの人が通ってきてくれて世間話をしてくれたのが、とても嬉しかったです。」
これを観たとき、思いついたので上司に進言しました。
「株で顧客に儲けさせるなんて証券マンにはほとんど不可能なことなので、営業マンに介護の資格を取らせて、老人の役に立てば、見返りとして金融商品を買ってくれるかもしれませんよ。親会社に言ってみたらどうですか?」
もちろん、却下されました。
でも、お金のためだけではなくて、何らかの形で顧客の役にたって「ありがとう」と言われることもモーチベーションとして重要かとは思っています。昔、たまたま営業のかたが不在で代わりにとったクレームの電話で1時間ぐらい顧客と話し込み、商品性や市場環境の説明を一からして、最後には「ありがとう」と言ってもらったときは嬉しかった記憶があります。小手先の付け焼刃的な技術より、誠意は伝わるものと思っています。
昔、尊敬していた上司のかたが言っていました。
「目先の成績や会社のために顧客を裏切ったら、この業界では生きていけなくなるぞ。例え会社の方針に逆らったとしても。方針が気に入らなければほかの会社に行けばいいだけだからな」
一般的には、例え反社会的行動であっても、会社の方針に従っていれば、会社内では生きていけます。トカゲのシッポきりに会わなければ。しかし、その会社自体が顧客からそっぽを向かれ、存続できなくなれば話は変わりますね。
余談ですが、銀行では、暴力団関係者などを「反社会的勢力」という表現で、口座を作ることを拒否したりします。でも、銀行の方がよっぽど反社会的勢力なのではと思ったこともあります。ヤクザはたしか横暴なお上から民衆を守るための自警団が発祥だったと本で読んだことがありますが、時代が移るにつれて、組織の維持のために本来の役目から変容するものは多いですね。目的を見失った組織は無理せずになくなればいいのではと思いますが、現実はそうでもないようです。
仕事というのは通常、顧客というものが存在し、一般的には顧客満足が得られなければ成り立たなくなります。顧客の満足をどのように得るかということには、様々な方法が考えられますが、おおまかには以下の通りです。
①本業で役に立つ
②巧妙な詐欺行為を行い、顧客に勘違いをさせる
③仕事とは関係ないことで役に立つ
①はそうあれば良い理想的な状態、②は意図してか結果的にそうするケースも考えられますが詐欺が発覚した時が困ります。そして③もそれなりに有効かと思っています。分かりやすい例でいえば、釣りバカ日誌の浜ちゃんのようなスタイルのことです。
ずいぶん前ですが、山一證券という証券会社が倒産しました。実は、倒産前に東京の中央区新川に本社が移転したのですが、その近辺は倒産ストリートと一部には言われてました。当時私の会社のオフィスは隣の茅場町でした。、新川はちょっと外れにあって家賃も安いようですが、山一がこんなところに移ってくるのかと驚いたものです。
当時は、それなりにニュースで大きく取り上げられましたが、印象に残ったニュース映像がありました。山一株などを購入していた、品のある老婦人がインタビューを受けていました。そのかた曰く「たしかに株で損はしましたけど、週に数回、若い男性の営業マンの人が通ってきてくれて世間話をしてくれたのが、とても嬉しかったです。」
これを観たとき、思いついたので上司に進言しました。
「株で顧客に儲けさせるなんて証券マンにはほとんど不可能なことなので、営業マンに介護の資格を取らせて、老人の役に立てば、見返りとして金融商品を買ってくれるかもしれませんよ。親会社に言ってみたらどうですか?」
もちろん、却下されました。
でも、お金のためだけではなくて、何らかの形で顧客の役にたって「ありがとう」と言われることもモーチベーションとして重要かとは思っています。昔、たまたま営業のかたが不在で代わりにとったクレームの電話で1時間ぐらい顧客と話し込み、商品性や市場環境の説明を一からして、最後には「ありがとう」と言ってもらったときは嬉しかった記憶があります。小手先の付け焼刃的な技術より、誠意は伝わるものと思っています。
昔、尊敬していた上司のかたが言っていました。
「目先の成績や会社のために顧客を裏切ったら、この業界では生きていけなくなるぞ。例え会社の方針に逆らったとしても。方針が気に入らなければほかの会社に行けばいいだけだからな」
一般的には、例え反社会的行動であっても、会社の方針に従っていれば、会社内では生きていけます。トカゲのシッポきりに会わなければ。しかし、その会社自体が顧客からそっぽを向かれ、存続できなくなれば話は変わりますね。
余談ですが、銀行では、暴力団関係者などを「反社会的勢力」という表現で、口座を作ることを拒否したりします。でも、銀行の方がよっぽど反社会的勢力なのではと思ったこともあります。ヤクザはたしか横暴なお上から民衆を守るための自警団が発祥だったと本で読んだことがありますが、時代が移るにつれて、組織の維持のために本来の役目から変容するものは多いですね。目的を見失った組織は無理せずになくなればいいのではと思いますが、現実はそうでもないようです。
Posted by 木原 昌彦 at
20:11
│Comments(0)
2016年04月23日
選挙権は何歳から?

歴史が好きです。数年前から歴女(歴史好きの女性)というかたがたがいるようですが、失礼ながら、正直ファッションの一つのようなもので表面的かつ教科書的な感じがしています。アイドルの代用品として坂本龍馬や沖田総司を使っているだけのような気もします。
動物と人間の違いで、人間には歴史があると言われることがあります。文字というか文献が残っている場合が歴史、それ以前は伝説と言われます。しかし、中学や高校で習った教科書の歴史にはあまり興味が持てませんでした。高校生の時に塩野七生女史の「ローマ人の物語」というシリーズものが開始され、イタリアの織田信長(?)である、チェーザレ・ボルジアの生涯を描いた、「チェーザレ・ボルジア あるいは優雅なる冷酷」という本で一気に、同女史の本にはまりました。自分が読んだ小説や専門書は裏歴史的なものであったので、歴史のテストにはほとんど役立たずではありました。はい!覚えたり、暗記するのは苦手な分野です。
私は経験則というのをあまり信用していません。一人の人間が生きているのはたかだか数十年であるため、そんな短い期間で、経験とやらから普遍的なことを発見するのはかなり困難であると考えています。プロイセンの鉄血宰相ビスマルクの言によると「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」というのがあります。自分の経験だけではなく、他人の経験、つまり歴史から学ぶことは多いのかとも思います。経験則とは、限定された期間の限定された環境でのみ通用するのではないでしょうか?まあでも、歴史が繰り返されるのは人間が全体として歴史から学んでいないからかもしれません。
話は変わりますが、このところ、憲法改正とか騒がれています。私は民主制とか民主政というものをあまり信用していません。人間にはまだまだ高級な概念ではないかとも思っています。常識という言葉と同様に、大多数のひとが考えている(単に感じている?)のが、必ずしも正しいとは思えないからです。どちらかというと君主制のほうが君主やブレーンが有能であれば、スピード感のある対応が可能かと思っています。もっとも、世襲であれば、親が有能でも子供が有能とは限りませんので、古代中国であったらしい 禅譲が理想でしょう。民主制とか共和制であっても、民主政が衆愚政となったり、ファシズムに発展することは過去の歴史から有り得ますので、民主的ということが必ずしも万能とは思えません。
しかし、民主制であってもそれなりの手続きがあればそれなりに機能はするとも思っています。それは選挙の有権者がそれなりに見識を持っているという前提が必要です。選挙権は何歳から付与するべきかというナンセンスな議論もありますが、年齢というのは名目的な数値にしか過ぎす、名目に対する実質が重要です。GDPなどもそうですね。
持論ですが、選挙権を付与する前提で、人類の歴史とか政治思想の種類や発生過程、メリット、デメリットなどに関する試験を設け、合格点は9割くらいにしたらいいのではと思っています。もちろん受験資格は設定しないということにして誰でも受けられるのであれば一定の平等感は確保できるかと思います。もちろん平等なんていうのは幻想であると思いますが。
テキストとしてお勧めしたいのは、田中芳樹原作の「銀河英雄伝説」です。ファンタジー小説かとも思われますが、よく練られており、政治思想についての勉強もできるかと思いますし、エンターテイメントとしても秀作です。歴史の小難しい本を読むより効果的かと考えます。新書版で本編10巻、外伝4巻あります。原作を忠実に再現したアニメもあります。とりあえず、アニメのDVDのリンクを貼っておきます。
 ・堀川亮・富山敬・広中雅志・若本規夫・森功至・納谷悟朗・村越伊知郎・宮内幸平・阪修全巻セ... |
もっとも、なぜかYoutubeでも観れます…
https://www.youtube.com/watch?v=Vqnqwt65BF8
2016年04月22日
絵に書いた餅より食べれる餅?

運用会社で経済分析の仕事をしていた20代の頃、毎月日米のマクロ経済の予想のレポートを書いていました。様々な経済指標を時系列でチェックし、行われている経済政策を絡めて経済が上向くか下向くかなどを予測していました。当時は結果的に、日本経済に対しては絶望感を持ち続けてました。客観的に見て良くなる要素がほとんど見当たらず、政府の経済政策も目先のことばかりに追われており、その効果も一過性のものが多く、すぐにまた状況は悪くなっていきました。
もう亡くなられましたが、当時一人だけ、この人が総理になれば日本は経済状態がよくなるのではと期待をかけていた人物がいたのですが、総裁選の前にご病気になり、亡くなられて残念な思いをしたことがあります。やはりいい人(?)は早死にしますな。もしかしたら実は暗殺されたのかもしれませんが。
私がずっと日本経済に対して弱気のレポートを書いていたので、飲みの席で上司(九州大学法学部卒の元証券マン)にこんなことを言われました。
上司 「あのな。お前はなんでそんなに弱気なんだ?」
私 「理由はレポートに書いてありますけど…読まれてませんか?」
上司 「小難しいことはどうでもいいんだよ。とにかく、もっとみんなが元気になるようなレポートを書けよ」
私 「うーん…ここは運用会社であって政府の経済政策を担当しているわけではないので、仮に私がこんな経済政策をすれば良くなると思っても、実行できないのであれば意味がないと思いますが」
上司 「とにかく、日本経済はよくなるんだよ」
私 「そう願いたいですが、その理由はなんですか?」
上司 「それは…偉い人がいろいろ考えてくれて、良くなるんだよ。バブルが崩壊して俺はもう10年以上も我慢している。もうそろそろいいだろ!」
私 「(うーん…全く意味をなしていないような)そうなるといいですねえ。」
いいアイデアがあったとしても、実行できなければ絵に書いた餅ですね。
たまに、どうあるべきかという議論で熱くなることもありますが、最近はなるべく避けようと思っています。
まあ、実現性の高いことを考えるのに時間を使う、もしくは、どうなるべきかではなく、どうなるのかということを冷静に予測し、個人的な対処の方法を考えることに時間を使いたいと考えています。
冷めてめているのかな?やはり、癒し系ではなくて冷やし系!
Posted by 木原 昌彦 at
05:18
│Comments(0)
2016年04月22日
小説の効用?
子供の頃、タレントのタモリさんが言っていたことが記憶に残っています。
「よく小説で作者は何が言いたいかって質問は馬鹿げている。言いたいことがあるなら、小説なんてまどろこしいことしないでストレートに言えばいい」
当時これに共感していました。子供の頃は本の虫で、古典を含めて小説もよく読みましたが、単純にエンターテイメントのためで特に深くは考えていませんでした。国語の授業などで、こういった質問があるとつまらんなあと思っていました。読書感想文を書くのも苦手でした。指定図書にたいした内容とか意味があるとは思えなかったからです。
30歳の頃、当時在籍していた会社の役員と全部門長が出席する会議向けに資料を作っていましたが、ある時、上司から「お前の資料はわかりにくいからなんとかしろ」と言われました。その上司の意図がよくわからなかったのですが、ほとんどはマトリックスとグラフで文章はあまり載せていませんでした。言い訳としては、文章よりも明確な事実である数字やグラフのほうが直感的にわかりやすいと思っていたからです。上司には「何がわかりにくいのかがよくわかりません」と答えると「うちの会社の役員は証券マン上がりなので、そんな数字や専門的なグラフなどの表現の羅列があっても意図を理解できないんだよ。かと言って長文にしても同じだから、グラフに吹き出しをつけて端的なコメントを入れるようにしろ」と言われました。次回以降その通りにしたら、なんだか漫画を書いているような気分になりました。
でも、その時に反省したのは、言いたいことをいうのが目的なのか伝えたいことが目的なのかということです。言いたいことはだれでも言えますが、それを多くのひとに伝えて、理解してもらい、世の中(?)をよりよくするためには工夫がいるかと思います。もっとも、部分的な真実のみを表現すると、想像力豊かなひとは別にして誤解を招くことも多いと思われます。
一番楽で誤解を招かないのは数式で表現することですが、誤解されずとも理解もされない可能性が高いです。多くのひとに理解してもらうには共感できるストーリーが効果的かと思われます。子供向けのイソップ物語などのように。
私はまだ経験不足の若輩者ですが、50歳を目標に小説を書こうと思っています。まあ実体験が元になる私小説かもしれません。ファンタジー官能小説の可能性もあります。テーマは「人間とは何か」ということで、悪人が成功し、善人が不幸になるとか、悪人が結局は世界を救うといった内容にして、高校生の時に太宰治の小説をもじって「人間合格」というタイトルを思いつきましたが、最終的な結論もプロセスも未だに構想中です。構想と素材が揃ったら書いてみようかと思っています。まだまだ勉強することは多いかと思いますが…
余談ですが、中学生の時の国語のテストである回答に△をつけられ、理由を聞いたら、担当の先生に「回答の意味がよくわからない」と言われたことがあり、それ以降はそのような可能性があると思ったときには回答に✽印をつけて欄外に脚注もつけてました。
「よく小説で作者は何が言いたいかって質問は馬鹿げている。言いたいことがあるなら、小説なんてまどろこしいことしないでストレートに言えばいい」
当時これに共感していました。子供の頃は本の虫で、古典を含めて小説もよく読みましたが、単純にエンターテイメントのためで特に深くは考えていませんでした。国語の授業などで、こういった質問があるとつまらんなあと思っていました。読書感想文を書くのも苦手でした。指定図書にたいした内容とか意味があるとは思えなかったからです。
30歳の頃、当時在籍していた会社の役員と全部門長が出席する会議向けに資料を作っていましたが、ある時、上司から「お前の資料はわかりにくいからなんとかしろ」と言われました。その上司の意図がよくわからなかったのですが、ほとんどはマトリックスとグラフで文章はあまり載せていませんでした。言い訳としては、文章よりも明確な事実である数字やグラフのほうが直感的にわかりやすいと思っていたからです。上司には「何がわかりにくいのかがよくわかりません」と答えると「うちの会社の役員は証券マン上がりなので、そんな数字や専門的なグラフなどの表現の羅列があっても意図を理解できないんだよ。かと言って長文にしても同じだから、グラフに吹き出しをつけて端的なコメントを入れるようにしろ」と言われました。次回以降その通りにしたら、なんだか漫画を書いているような気分になりました。
でも、その時に反省したのは、言いたいことをいうのが目的なのか伝えたいことが目的なのかということです。言いたいことはだれでも言えますが、それを多くのひとに伝えて、理解してもらい、世の中(?)をよりよくするためには工夫がいるかと思います。もっとも、部分的な真実のみを表現すると、想像力豊かなひとは別にして誤解を招くことも多いと思われます。
一番楽で誤解を招かないのは数式で表現することですが、誤解されずとも理解もされない可能性が高いです。多くのひとに理解してもらうには共感できるストーリーが効果的かと思われます。子供向けのイソップ物語などのように。
私はまだ経験不足の若輩者ですが、50歳を目標に小説を書こうと思っています。まあ実体験が元になる私小説かもしれません。ファンタジー官能小説の可能性もあります。テーマは「人間とは何か」ということで、悪人が成功し、善人が不幸になるとか、悪人が結局は世界を救うといった内容にして、高校生の時に太宰治の小説をもじって「人間合格」というタイトルを思いつきましたが、最終的な結論もプロセスも未だに構想中です。構想と素材が揃ったら書いてみようかと思っています。まだまだ勉強することは多いかと思いますが…
余談ですが、中学生の時の国語のテストである回答に△をつけられ、理由を聞いたら、担当の先生に「回答の意味がよくわからない」と言われたことがあり、それ以降はそのような可能性があると思ったときには回答に✽印をつけて欄外に脚注もつけてました。
Posted by 木原 昌彦 at
03:38
│Comments(0)
2016年04月21日
アイ・マイ・ミー?
何度か書きましたが、私は世間一般的な表現(?)を借りれば、いわゆる理系崩れです。はい!高校3年にして数学的センスがないということに気がつきました。もっとも、私がいたのは普通科ではなくて理数科というクラスでしたが、クラスメートの半数近くは文転したような記憶があります。中学レベルの数学が出来た程度で理系と勘違いしたのは、しかたのないことかもしれません。もっとも、ひとを文系、理系と区別するのはちょっとナンセンスな気がします。いわゆる文系のかたでも英語などの外国語はともかく、日本語が苦手なひとも散見されますので。
以前は、曖昧なことが嫌いで白黒はっきりさせたいほうで、グレーであっても白黒の比率を明確にしたいほうでした。そして唯物論者かつ決定論者的なところがありました。
曖昧を数学的に表現するといったファジー理論(まあ実際は乱数と同様に擬似的なもの)というのが、すいずん前に存在し、家電にも応用されていたことがあります。ほかには、ニューロとか1/fのゆらぎといったものも家電に応用されましたね。最近はそういうのはないのでしょうか?
一時期、複雑系とか、カオス理論というのが脚光を浴び、投資にも役立たせようという動きがありました。たしか行動経済学という分野も関連していました。しかし観念論的で、実践的なものは見かけませんでしたが、その後進化を遂げているかもしれません。当時、会社の後輩に「そのうちカオス洗濯機とか出るんじゃないのかな?洗ってみないとわかりませんとか」と言ったら、後輩曰く「いやいや、たぶん洗濯するとカルマン渦がプリントされますよ」とのことでした。カオス家電と銘打ったものは見かけませんでしたが、どこかで応用されているのかな?
しかし、社会人になってから投資理論の専門書とか読むと、確率統計はともかく、行列とかベクトルが出てきたのには困りました。しかたないので30歳のころ、基礎から復習しましたが、高校生の時ちゃんと数学やっておけば良かったと反省しました。
世の中ほとんどの問題は数学と論理で解決できるとは考えています。
しかしネックは、ジレンマが発生する場合の目的の優先順位ですね。倫理とか感情とか…いずれも気分の問題ですが…
以前は、曖昧なことが嫌いで白黒はっきりさせたいほうで、グレーであっても白黒の比率を明確にしたいほうでした。そして唯物論者かつ決定論者的なところがありました。
曖昧を数学的に表現するといったファジー理論(まあ実際は乱数と同様に擬似的なもの)というのが、すいずん前に存在し、家電にも応用されていたことがあります。ほかには、ニューロとか1/fのゆらぎといったものも家電に応用されましたね。最近はそういうのはないのでしょうか?
一時期、複雑系とか、カオス理論というのが脚光を浴び、投資にも役立たせようという動きがありました。たしか行動経済学という分野も関連していました。しかし観念論的で、実践的なものは見かけませんでしたが、その後進化を遂げているかもしれません。当時、会社の後輩に「そのうちカオス洗濯機とか出るんじゃないのかな?洗ってみないとわかりませんとか」と言ったら、後輩曰く「いやいや、たぶん洗濯するとカルマン渦がプリントされますよ」とのことでした。カオス家電と銘打ったものは見かけませんでしたが、どこかで応用されているのかな?
しかし、社会人になってから投資理論の専門書とか読むと、確率統計はともかく、行列とかベクトルが出てきたのには困りました。しかたないので30歳のころ、基礎から復習しましたが、高校生の時ちゃんと数学やっておけば良かったと反省しました。
世の中ほとんどの問題は数学と論理で解決できるとは考えています。
しかしネックは、ジレンマが発生する場合の目的の優先順位ですね。倫理とか感情とか…いずれも気分の問題ですが…
Posted by 木原 昌彦 at
23:05
│Comments(0)
2016年04月21日
名はタイ(テイ?)を表す?他意?君の名は?
投資信託を設定・運用している会社に3社、全部で15年在籍していました。アナリストは7年くらいで、ほかは経営企画室のような部署、コンプライアンスやリスク管理、商品企画、投資顧問営業やクライアントサービス、パフォーマンスを分析する部署などに所属し、やらなかったのは計理(経理とは違います)くらいですが、自分でも基準価額の計算をたまにやっていました。
ところで投資信託には、なぜか愛称というものをつけることがあります。そういう場合には、積極的にアイデアを出しましたが、採用されたのは1度しかありません。
大学を卒業して最初に入った運用会社(11年在籍)は、販売会社である証券会社が親会社でした。ある時、社運(?)を賭けた商品(正確には製品ですが)を大体的に売り出そうということで、販売していただいている証券マンの方々に愛称を募集するということになりました。そして、出された案の一つに「あすなろ」というのがあってびっくりしました。
「あすなろって…たぶん井上靖の『あすなろ物語』のあすなろだよな…それって明日には檜になろうと頑張っても、結局なれないという、あの「あすなろ」だよな。『あすなろ白書』ってドラマもあるらしいけど、そっちは観たことないなあ。案を出したひとの教養をちょっと疑いたくなるけど、もしかして運用の失敗を願っている確信犯かも?」
マズイと思ったので、上司に進言して、候補から外すべきだと主張しましたが、いつも生意気だったので主張が通らず…なんと、その「あすなろ」が愛称になりました。「名は体(テイ?)を表す」とも、いいますが、結果としては名前の通りになりました。その会社は親証券会社が当時の日本興業銀行(第一勧銀と富士と合併して現在みずほ銀行)の命令で合併すると同時に合併しました。その後、親会社が吸収合併されて、みずほ証券になったものの、その運用会社は未だに合併されずにしぶとく残っています。ちょっと特徴のある会社でしたので。うーん…やめなければ良かったなあ…後悔先立たず…
話は変わりますが、私の名前は「〇彦」といいます。父は「源〇」で〇には同じ字が入ります。私の家系は、亡き父から聞いたところによると、大内氏を追いやったあとに、毛利に滅ぼされた陶晴賢の家来だったようで、陶晴賢が死んだあとに、毛利からオファーを受けたものの、武士は2君につかえずということで集団自決したらしいですが、一人だけ生き残ったひとがいて、毛利の部下にはならず下野し、その後、豪農かつ商売人(なぜか江戸時代には帯刀も許されたようです)になったようです。そして時代は流れ、農地改革の時に政府に土地を取り上げられたと聞いています。
本家の長男には、「源」という字をつける風習がありましたが、既に本家の直系はいなくなり、私の父が生まれた時に本家を継ぎました。私が産まれた時に本家筋の祖母が、「源」をつけるように迫ったらしいですが、父は聞き入れずに私に〇彦とつけました。てっきり父の1字をとったものと思っていましたが、ある時、一緒に酒を飲んだ時に聞いたら、意外な真相でした。父の叔父にあたる人で〇助というひとがいたそうで、早世したものの、当時、天才児と言われていたそうです。同じ字だけど、気持ちは父の叔父から取ったと言っていました。大叔父の生まれ変わりとして…でも私は天才でもなく、昔の上司に言われたところによると長生きするみたいですが…
そういえば、昔の上司で一流大学(たしか一橋)出身のかたにこんなことを言われました。
上司 「俺はいわゆる秀才だが、お前はテンサイだな!そのふざけた発想は!」
私 「いやー!それほどのことは…ありますよ!」
上司 「天の災いのほうだよ!」
私 「ええ!できれば、サトウ大根でお願いしますー」
上司 「…」
はい!今日も落ちはありませんが、最後に11年ほど在籍した会社に敬意を表してサイトのURLを…
http://www.shinkotoushin.co.jp/
ところで投資信託には、なぜか愛称というものをつけることがあります。そういう場合には、積極的にアイデアを出しましたが、採用されたのは1度しかありません。
大学を卒業して最初に入った運用会社(11年在籍)は、販売会社である証券会社が親会社でした。ある時、社運(?)を賭けた商品(正確には製品ですが)を大体的に売り出そうということで、販売していただいている証券マンの方々に愛称を募集するということになりました。そして、出された案の一つに「あすなろ」というのがあってびっくりしました。
「あすなろって…たぶん井上靖の『あすなろ物語』のあすなろだよな…それって明日には檜になろうと頑張っても、結局なれないという、あの「あすなろ」だよな。『あすなろ白書』ってドラマもあるらしいけど、そっちは観たことないなあ。案を出したひとの教養をちょっと疑いたくなるけど、もしかして運用の失敗を願っている確信犯かも?」
マズイと思ったので、上司に進言して、候補から外すべきだと主張しましたが、いつも生意気だったので主張が通らず…なんと、その「あすなろ」が愛称になりました。「名は体(テイ?)を表す」とも、いいますが、結果としては名前の通りになりました。その会社は親証券会社が当時の日本興業銀行(第一勧銀と富士と合併して現在みずほ銀行)の命令で合併すると同時に合併しました。その後、親会社が吸収合併されて、みずほ証券になったものの、その運用会社は未だに合併されずにしぶとく残っています。ちょっと特徴のある会社でしたので。うーん…やめなければ良かったなあ…後悔先立たず…
話は変わりますが、私の名前は「〇彦」といいます。父は「源〇」で〇には同じ字が入ります。私の家系は、亡き父から聞いたところによると、大内氏を追いやったあとに、毛利に滅ぼされた陶晴賢の家来だったようで、陶晴賢が死んだあとに、毛利からオファーを受けたものの、武士は2君につかえずということで集団自決したらしいですが、一人だけ生き残ったひとがいて、毛利の部下にはならず下野し、その後、豪農かつ商売人(なぜか江戸時代には帯刀も許されたようです)になったようです。そして時代は流れ、農地改革の時に政府に土地を取り上げられたと聞いています。
本家の長男には、「源」という字をつける風習がありましたが、既に本家の直系はいなくなり、私の父が生まれた時に本家を継ぎました。私が産まれた時に本家筋の祖母が、「源」をつけるように迫ったらしいですが、父は聞き入れずに私に〇彦とつけました。てっきり父の1字をとったものと思っていましたが、ある時、一緒に酒を飲んだ時に聞いたら、意外な真相でした。父の叔父にあたる人で〇助というひとがいたそうで、早世したものの、当時、天才児と言われていたそうです。同じ字だけど、気持ちは父の叔父から取ったと言っていました。大叔父の生まれ変わりとして…でも私は天才でもなく、昔の上司に言われたところによると長生きするみたいですが…
そういえば、昔の上司で一流大学(たしか一橋)出身のかたにこんなことを言われました。
上司 「俺はいわゆる秀才だが、お前はテンサイだな!そのふざけた発想は!」
私 「いやー!それほどのことは…ありますよ!」
上司 「天の災いのほうだよ!」
私 「ええ!できれば、サトウ大根でお願いしますー」
上司 「…」
はい!今日も落ちはありませんが、最後に11年ほど在籍した会社に敬意を表してサイトのURLを…
http://www.shinkotoushin.co.jp/
Posted by 木原 昌彦 at
21:50
│Comments(0)
2016年04月21日
どちて?
小学生のころ、「一休さん」というアニメがありましたが、正直つまらなく感じていました。自宅に帰ってテレビをつけた時にこの番組が画面に出るととても残念な気分になりました。毎週楽しみにしていた「8時だよ全員集合」が器械体操の日である時と同じくらい残念でした。
たしか中学生のころ、クラスメートに「どちて坊や」と言われていた時期があったと記憶しています。これは、一休さんに出てくるキャラクターで、誰かが何かを言うと「どちて?」と聞き返し、答えてもらってもそれに対して「どちて?」と理由を求める質問を繰り返すという小さな子供でした。たしか、頓智(屁理屈とどう違うのか不明)自慢の一休さんもこの子供が苦手だったような気がします。大人は疑問に思ったことがあっても、周りの空気を読んであえて聞かずに、なんとなく周りに合わせることを余儀なくされることが多いかと思います。下手に疑問を口に出すことでトラブルに巻き込まれることもままあります。疑問に対する答えが、ブラックな大人の事情であるケースのほか、単に誰も考えずに習慣(因習?)として行動している可能性も否定はできません。しかしながら多くの場合、考えても何も解決しないこともままあるので、大人は大人の対応をしている訳です。
東京からUターンして中途入行した銀行に、高校の後輩が数名いました。ある時、業務上の事務処理の方法で不合理に思ったことがあり、特に深く考えずに、その後輩に聞いてみました。その後輩からは「キハラさん、実はそれは気づいてはいけないことなんです。気づいても口に出してはいけないことなんです。」との答えが返ってきました。かつて、どちて坊やだった私も、それ以上聞くのはやめておきました。
中学の道徳(まだこの教科は存在するのかな?)の教科書に、ギリシャの哲学者ソクラテス(弟子のプラトンが書いたのが「ソクラテスの弁明」)のことが書かれていました。有名な話なのでご存知のかたも多いかと思いますが、彼は、あらゆる人(若者が主な対象だったかな?)に様々な質問を投げかけ、その人たちが物事をより深く考えるように仕向けたことが原因で、最後は裁判にかけられ、毒を飲んで死ぬという刑罰を受けました。昔も今もそうかもしれませんが、支配階級のかたがたは、(もしかしたら好意で?)情報を操作したり、民衆や大衆(定義がいまいち不明)が物事を深く考えないように仕向ける傾向が見受けられます。まあ、アジ演説や恐怖政治という方法もあります。
今日もなんとなく脈絡なく書いてしまいました。まあ、結論としては、「雉も鳴かずば撃たれまい」か、ガリレオの「それでも地球は回っている」のお好きな方をお選びください。
ちなみに私は、正しいとか正しくないとか考えても結論がでずに眠れなくなくこともあるので、最近は面白ければそれでいいと考えています。高杉晋作曰く「つまんないから、面白くしようぜ!(現代語版)」
たしか中学生のころ、クラスメートに「どちて坊や」と言われていた時期があったと記憶しています。これは、一休さんに出てくるキャラクターで、誰かが何かを言うと「どちて?」と聞き返し、答えてもらってもそれに対して「どちて?」と理由を求める質問を繰り返すという小さな子供でした。たしか、頓智(屁理屈とどう違うのか不明)自慢の一休さんもこの子供が苦手だったような気がします。大人は疑問に思ったことがあっても、周りの空気を読んであえて聞かずに、なんとなく周りに合わせることを余儀なくされることが多いかと思います。下手に疑問を口に出すことでトラブルに巻き込まれることもままあります。疑問に対する答えが、ブラックな大人の事情であるケースのほか、単に誰も考えずに習慣(因習?)として行動している可能性も否定はできません。しかしながら多くの場合、考えても何も解決しないこともままあるので、大人は大人の対応をしている訳です。
東京からUターンして中途入行した銀行に、高校の後輩が数名いました。ある時、業務上の事務処理の方法で不合理に思ったことがあり、特に深く考えずに、その後輩に聞いてみました。その後輩からは「キハラさん、実はそれは気づいてはいけないことなんです。気づいても口に出してはいけないことなんです。」との答えが返ってきました。かつて、どちて坊やだった私も、それ以上聞くのはやめておきました。
中学の道徳(まだこの教科は存在するのかな?)の教科書に、ギリシャの哲学者ソクラテス(弟子のプラトンが書いたのが「ソクラテスの弁明」)のことが書かれていました。有名な話なのでご存知のかたも多いかと思いますが、彼は、あらゆる人(若者が主な対象だったかな?)に様々な質問を投げかけ、その人たちが物事をより深く考えるように仕向けたことが原因で、最後は裁判にかけられ、毒を飲んで死ぬという刑罰を受けました。昔も今もそうかもしれませんが、支配階級のかたがたは、(もしかしたら好意で?)情報を操作したり、民衆や大衆(定義がいまいち不明)が物事を深く考えないように仕向ける傾向が見受けられます。まあ、アジ演説や恐怖政治という方法もあります。
今日もなんとなく脈絡なく書いてしまいました。まあ、結論としては、「雉も鳴かずば撃たれまい」か、ガリレオの「それでも地球は回っている」のお好きな方をお選びください。
ちなみに私は、正しいとか正しくないとか考えても結論がでずに眠れなくなくこともあるので、最近は面白ければそれでいいと考えています。高杉晋作曰く「つまんないから、面白くしようぜ!(現代語版)」
Posted by 木原 昌彦 at
02:35
│Comments(0)
2016年04月21日
企業内テロリスト?
以前、会社の先輩に「お前はテロリストみたいだな!」と言われました。実は(似非?)マキャベリストで目的のためなら手段は選ばないという面もあります。そう!効率的、効果的なことを重要視しています。倫理的な問題も生じかねませんが、まあ倫理というのもおそらく気のせいで状況に応じて変化するものかと思われます。
若いころ、上司や役員などの経営陣に意見具申したりしてもなかなか通らない時がありました。もっとも、私の意見が間違っていたり、時期尚早だったこともあるかとは思います。ある時、経営方針に関して先輩に意見を述べたら、「それはお前が考えることではないよ。そんなこと言ってたら、越権行為だな」と言われました。「おっしゃるとおりですが、今の経営陣のやりかたでうまくいくと思いますか?」と聞いたら「そんなことは思わないが、意見を言う暇があったら、もっとまともな会社に転職(転社?)したほうが労力が少なくて済むと思うけどな」と返されました。もちろん、その考え方もある価値観のもとでは正しいかとは思います。
組織にいる以上、そこの文化や因習、ルールを守るということは基本的には正しいのかもしれません。まあ、①とにかく我慢する(一番楽な方法?)②組織を変えるために行動する③辞めてしまう(楽ですが、辞めたあとにほかの会社に入った場合、同様な問題がおそらく生じる)、④とりあえず我慢して出世してから自分の思うとおりにやる(長期戦かつ不確実性も高いような?)などの選択肢がありますね。
私は、最近はのんびりモードですが、若い頃はせっかちでした。結果として取った行動は、ゲリラ戦法かテロ行為です。前者についてはまた今度書こうかと思いますが、後者は要するにあえてトラブルを発生させるということです。
社内的なトラブルもあれば対外的なトラブルもあります。なるべく後者は避けたいとは思いますが、ケースバイケースです。つまり、現体制ではこんな問題が起きますよと意見具申しても、相手にされないのであれば、実際にトラブルを起こしてしまうほうが、経営陣に潜在的(事後的には顕在?)なリスクを認識させることができ、比較的早い対応がなされることが想像されます。
具体的な社名や時期などについてはあえて伏せますが、何度か実行したことがあります。結果は比較的良好でした。もっとも、会社を辞めるハメになったこともありますが、まあそれも想定内です。
昔直訴したり、一揆した農民さんたちは死罪でしたね。磔の刑だったかな…まあ現代ではそれで殺されるという可能性は低いかと…
そして方法論のひとつとしては有効であると愚考します。
クビを覚悟した時には、後輩に「俺の屍を越えてゆけ」と伝えておきました。
若いころ、上司や役員などの経営陣に意見具申したりしてもなかなか通らない時がありました。もっとも、私の意見が間違っていたり、時期尚早だったこともあるかとは思います。ある時、経営方針に関して先輩に意見を述べたら、「それはお前が考えることではないよ。そんなこと言ってたら、越権行為だな」と言われました。「おっしゃるとおりですが、今の経営陣のやりかたでうまくいくと思いますか?」と聞いたら「そんなことは思わないが、意見を言う暇があったら、もっとまともな会社に転職(転社?)したほうが労力が少なくて済むと思うけどな」と返されました。もちろん、その考え方もある価値観のもとでは正しいかとは思います。
組織にいる以上、そこの文化や因習、ルールを守るということは基本的には正しいのかもしれません。まあ、①とにかく我慢する(一番楽な方法?)②組織を変えるために行動する③辞めてしまう(楽ですが、辞めたあとにほかの会社に入った場合、同様な問題がおそらく生じる)、④とりあえず我慢して出世してから自分の思うとおりにやる(長期戦かつ不確実性も高いような?)などの選択肢がありますね。
私は、最近はのんびりモードですが、若い頃はせっかちでした。結果として取った行動は、ゲリラ戦法かテロ行為です。前者についてはまた今度書こうかと思いますが、後者は要するにあえてトラブルを発生させるということです。
社内的なトラブルもあれば対外的なトラブルもあります。なるべく後者は避けたいとは思いますが、ケースバイケースです。つまり、現体制ではこんな問題が起きますよと意見具申しても、相手にされないのであれば、実際にトラブルを起こしてしまうほうが、経営陣に潜在的(事後的には顕在?)なリスクを認識させることができ、比較的早い対応がなされることが想像されます。
具体的な社名や時期などについてはあえて伏せますが、何度か実行したことがあります。結果は比較的良好でした。もっとも、会社を辞めるハメになったこともありますが、まあそれも想定内です。
昔直訴したり、一揆した農民さんたちは死罪でしたね。磔の刑だったかな…まあ現代ではそれで殺されるという可能性は低いかと…
そして方法論のひとつとしては有効であると愚考します。
クビを覚悟した時には、後輩に「俺の屍を越えてゆけ」と伝えておきました。
Posted by 木原 昌彦 at
00:01
│Comments(1)
2016年04月20日
愛だよ…愛!アイアイ?

ブログのプロフィールに、尊敬する人物として上杉鷹山を挙げています。それほどメジャーではないかもしれませんが、九州の小さな藩(先日、大学の先輩に教えてもらいましたが、現在の宮崎県にあったそう)から、東北の米沢藩にお姫様(ちなみに障害者だったとのこと)の婿養子として入り、藩主として改革を断行し財政を立て直した人物です。
私は学生の頃にとある本を買って読んだことで鷹山のことを知りました。本の詳しい内容は当然のことながらネタバレを避けて書きませんが、なかなかいい本だと思いました。鷹山のエピソードでは、比較的有名な言葉で「なせば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり」や「してみせて 言って聞かせて させてみる」などがあり、鷹山の思想には、現代にも通用し、かつ、ひとを慈しむというところが見受けられます。私は「過ちて改むるに憚ることなかれ」という論語にあった言葉が出てきたのに感銘を受けた記憶があります。つまり、「間違いに気づいたら非を認めて朝令暮改となっても訂正することに躊躇してはならない」ということですが、ひとは、そうすることで面子を失うというリスクはあるものの、面子なんかにこだわっていたら恥の上塗りをすることにもなりかねません。
そういえば、すいぶん前に、大河ドラマで直江兼続が主人公として出てたような気がしますが、どうも鷹山はかつて上杉藩で重鎮として活躍した兼続にも影響を受けたのではとも思いました。事実、兼続も似たような行動で藩の財政危機を乗り切ったようですし…ちなみに兼続の兜の前立ては「愛」という文字ですね。もちろん男女間の愛ではなく、仏教用語の慈愛のほうのようですが…
30代のころ、担当役員に意見具申をしても聞いてもらえなかったので、「じゃあ代わりにこの本を読んでください」と鷹山の本をお貸ししたことがあります。結果半年後くらいに意見が通ったことがあります。
私は女性に対して「愛している」などと言ったことは一度もありません。癒し系ならぬ冷やし系だからというよりは、自分が意味を理解している(つもり?)言葉以外は使うことに躊躇するからです。でも、娘がいたら使ってもいいな。誰か産んでくれないかな。できれば3人…このさい三つ子でもかまいません。既に名前も決めています「泪」「瞳」そして「愛」…キャッツアイ!
おまけ:私が買った本はハードカバーですが、実物は現在、山口県の実家の倉庫に保管してあります。個人的に利用している楽天で調べたら文庫版があったので、ブログの広告でしばらく紹介しておきます。