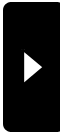2023年01月12日
株価指数について

世間にはいろいろ指数や比率といった指標というものがありますが、結果的な数値自体が独り歩きして誤解を招くこともあります。やはりどのような計算を経て出されたものか知っていたほうがいいと基本的には思っています。
株式市場についてニュースとか新聞によく出てくる指数として、日経平均もしくは225(日経平均株価225種)やTOPIX(東証株価指数)というものがありますが、この二つには顕著な(?)相違があります。前者は単純平均で、後者は加重平均という概念です。
単純平均とは、その名の通りデータ(この場合は構成している個別銘柄の株価)の単純な(?)平均をとったもの(もっとも資本移動などの際に連続性を維持するために除数という概念がある)です。後者の加重平均は、何らかの数値でウェイト付けして平均値を計算しますが、TOPIXの場合は時価総額(株価に発行済み株式数を乗じたももの)です。なお、時価総額によるウェイト付けから市場での流動性を勘案し、安定株主の比率を除いたものも存在しています。
その計算方法の相違から推測できますように、日経平均では値嵩株、TOPIXでは、大型株の価格変動に影響を受けます。私の勝手な印象ですが、海外も含めて前者の単純平均のほうが、メディアに出てることが多く、後者はまあ、専門家仕様(?)でしょうか。また、現物の株式には配当というものがあります、それを考慮に入れた配当込み指数というのも存在しており、年金運用の世界ではこちらをベンチマークなどに利用することが多いです。
投資信託などで、海外の資産に投資することが一般的となっておりますが、海外の指標と比較するときは、細かいようであるが同じような計算をしたものを利用したほうが良いのではと思っています。あと採用している為替レートなども細かいことをいえば影響します。もちろん、大勢には影響ないのではという意見ももちろんあるでしょう。まあ、ただの気分の問題ですが、些少な差異が、結果的に判断を左右することは有り得ます。
以前、パフォーマンスの計測や評価をしていた際によく利用していたのはMSCI(Morgan Stanley Capital Index)で、以下のURLで情報が取れます。ちなみにこちらは加重平均を採用しています。
http://www.msci.com/products/indices/performance.html
世界の多くの国をカバーしていますし、スタイル(Value、Growth)や規模、業種と言った分類別の指数も存在していて、上記のサイトからヒストリカルデータも入手可能なのでとても便利です。
2023年01月07日
テクニカルターム?

追記修正しましたので再度投稿します。
知人から専門用語が分かりにくいと指摘されたため、多少噛み砕こうかと思います。まあ、ググれば出てくる言葉とも思いましたが、資産運用関連の投稿に使用したテクニカルターム(専門用語)の意味をアフターサービスとして以下に記します。
まず、ロングとショートですが、前者は投資対象を買うことです。ロング・ポジションやロングオンリーなどの表現があります。後者は逆に「売り」のことで、信用売りや借り株、指数先物の売り建てを意味します。
続いてアセットクラスですが、これは投資対象となる資産の種類のことで、要は株式とか債券などどいった分類ですね。目的や状況によって分け方が異なることもあります。
そして、エクスポージャーです。英語で「晒す」ということで、リスクのある投資対象の組み入れ比率のことです。例えば100億円資産があったとして株式を90億円分組み入れたとしたら、株式エクスポージャーは90%です。もっとも、同時に株式指数先物を90%売り建てていたら、ネットのエクスポージャーは0%になります。他には外貨建て資産を組み入れている場合には外貨エクスポージャーという表現もあります。
次に、ベータです。これは比較的有名なので、ご存知のかたも多いかもしれませんが、個別株式やポートフォリオにおいて、日経平均や東証株価指数などに対する連動性です。対象の指数との相関係数に標準偏差の比を乗じるか、指数との共分散を指数の分散で除すると出てきます。おおまかに言うとベータが1.2の場合、指数が10%上昇すれば、その資産は12%上昇するというものですが、個別銘柄だと決定係数も低く不安定で、実務上は役にたたないケースも多いです。
今度は、ファクターですが、市場の変動要因をお互いに相関の無いように統計的に抽出したもので、有名どころとしてはBarra社(すでに合併してMSCI Barra)のファクターモデルというのがあり、リスクコントロールやリターンの要因分析などに使われます。他には運用会社が独自に収益予想のファクターモデルを作っていることが多くあります。
最後にスペシフィックリターンですが。上記のファクターで(結果論として)説明できないリターンのことで個別銘柄に特有の事情に起因するもの意味します。
以上こんなところですが、ほかにも分かりにくい用語がありましたらコメントいただければ返答いたします。
2023年01月02日
シャープレシオ?シャウプ勧告?

明けましておめでとうございます。本日は2023年初のオフです。自宅でお酒を飲んでのんびりしています。
さて前回と同じく資産運用関連投稿の加筆・修正でございます。
私は一時期、投資信託の運用会社でファンドの評価の仕事をしていたことがあります。投資信託の評価では、様々な指標が使われます。個人では、単純に●%上昇したとか、どれだけ儲かったということで良し悪しを判断される方もいるかもしれません。また、基準価額の水準がいくらだということで判断されるかたもいるかもしれません。しかし、リスクのある金融商品を評価するには、リターンのみでなく、(結果的な?)リスクも勘案しないと公平ではありません。
資産運用業界では、運用評価の一手段として「リスク調整後収益率(もしくはリターン)」という指標がいくつかあり、その中でも、初歩的で割と流通しているのがタイトルの「シャープレシオ」です。たしか考案したかたのお名前が語源だったような気がします。余談ですが、戦後に米国からシャウプさんというかた率いる使節団が来日して日本の税制について調査してましたね。私は昨年の冬から減税推進活動の一環として日本の税制の勉強会に参加していて現在テキストとして以下の内容を読んでいます。
http://www.rsl.waikei.jp/shoup/shoupr01.html
話をシャープレシオに戻しますが、計算としては超過収益率(収益率から安全資産の収益率を差し引きますが、現在の日本のような超低金利でれあば、実務上無視して、単純に収益率だけでもいいかもしれません)の平均値をリスクである収益率の標準偏差で除します。
同じリターンだとしても、リスクが高い場合には、この指標というか比率は、数値が低くなります。このあたりの説明は、「シャープレシオ」という言葉でクグれば出てきます。でも、なぜ自分のブログでわざわざ書いているかいうと、誤った使われ方を、見たり聞いたりして気になっていたからです。
結論から言うと、絶対的な数値はそれほど意味がないということです。たとえば「このファンドはシャープレシオが●●だから成績がいい」などとは言えません。しかし、単純に数値だけが独り歩きして説明されている場面もたまに見受けられます。
リスクもリターンもサンプルの取り方によって水準がブレますので、あくまで同じ期間での他者との比較のみに参考とできると考えます。
余談ですが、リターンがマイナスの場合にはこのシャープレシオは意味を成しません。リスクは正の数値なので、同じ(マイナス)リターンの場合、リスクが高いほうが、シャープレシオのマイナス数値が小さくなります。
一般に、比率といった数値は、様々な状況を大雑把に示していることがあり、それだけで判断するのは無理がありますので、シャープレシオよりは、リスクとリターンの散布図で見たほうがいいかもしれません。
投資信託の評価サイトであるモーニングスターは、類似したファンドのランキング評価でシャープレシオを主として使っています。シャープレシオだけですべてを語るのはもちろん乱暴ですが、ご自分がお持ちの投資信託が、類似したファンドに比べてどうなのか、ご参考までにご覧になってはいかがでしょうか?
http://www.morningstar.co.jp/fund/
2022年12月29日
分散効果?

先日アセットアロケーションについて投稿しました(以下URL)。
http://schole.chesuto.jp/e1701068.html
しかし、ちょっと消化不良気味な感じもするので、タイトルの「分散効果」について書きます。
昔から「資産三分法」と言われている言葉がありますね。「現金」「土地」「株」に資産を分けるということです。まあ、いわゆる「経験則」というものですね。
私は、あまり個人の経験則というものを信用していません。
一人の人間が生きているのは長くてもたかだか100年程度なので、そんな短い期間で普遍的な法則を見つけるというのは、かなり困難なのではと思っています。環境が変わると通用する方法論も変わりますが、成功体験などがあったりすると、それに固執しがちだったり、もしくは自分が理解できないことは最初から否定するということもあり得ます。結果的に全く根拠が見当たらない、「たまたま」の事象もあるのではと思っています。
話を戻しますが、分散効果が働くのはそれぞれの投資対象間において収益率の相関関係が低い場合です。統計というのは全体の中から切り出したサンプルでしかありませんが、時系列のデータがあれば、相関係数などを計算してみるといいでしょう。また、市場が分断されていたり、相関関係が低い理由になんらかのロジックが存在していればいいのですが、グローバリゼーションが進展していることもあり、以前に比べると多くの資産間で相関関係は高まっているようです。
また、分散させるにも、何を選ぶかと同時にウェイトのかけかたが重要です。もっとも、許容できるリスクや期待するリターンによって行動は変わってくると思います。
もちろん、これが「正解」というのは単純には存在しないとも思いますが、なぜ、その投資対象を選んだのか、そしてなぜそのウェイトなのかということは少なくともご自分の意図を反映させる必要があるのではと考えます。
理屈どおりにはいかないことも多くあるでしょうが、全く理屈を無視するのも危険なのではとも思われます。
そう言えば、以前、「ブンさん」っていうファンドがありましたが…まだご存命でしょうか?
2022年12月19日
あせって?アロケーション?

資産運用の世界では、アセットアロケーションという言葉が重要な位置を占めています。日本語では「資産配分」となります。
なぜ重要かというと、資産運用の結果に対して要因として最も影響があるものだからです。一般的な資産運用の成果の大部分を決める要因であるといっても、過言ではありません。
銀行や証券会社などで購入される公募の投資信託などでは、日本株を投資対象としたものは多くあります。もちろん、ユニークなテーマのファンドもあり、それはそれで存在価値はあるかもしれませんし、バリューやグロース、小型株といった特定のスタイルに注目するのも意味がないとは思いません。しかし、どのテーマやスタイルを選ぶかよりも日本株を買うかどうかという意思決定のほうが重要です。よく、TOPIXや日経平均といったベンチマークに勝ったとか負けたとかという議論もありますが、事実上多くのファンドは安定的にベンチマークに勝つのは、仕組み上、かなり困難であると思われますのでネット証券のノーロード(販売手数料がない)ファンドやコストの安いETFなどに投資するほうが(単純には)経済合理性はあるかと思われます。もっとも、多くの人間は経済合理性だけで物事を判断している訳ではないので一概には言えない部分はあるかと思われます。まあ、金融機関の窓口で資産運用のアドバイスを受けるのは、キャバクラで酒を飲むのと同様に「擬似恋愛」的な要素がありますが、あくまで「擬似」として楽しめるであれば、それでもいいでしょう。
やや話がそれたので、もとにもどしますが、資産運用の成果で最も重要な、「資産配分」で安定的かつ着実に成果を上げるということは至難の業であることも事実です。一昔前、タクティカル・アセット・アロケーション(TAA)やストラテジック・アセット・アロケーション(SAA)といった手法(?)ももてはやされましたが、結果として成果を上げたかどうかということも疑問があります。現実問題として、どの資産クラスが優位かということは事前にはわからないので、結論としては、いろいろ小難しいことを考えても、それほど意味はないような気もします。もっとも、分散投資を行うことにより、トータルのリスクを管理するという点では「教科書」的には意味はあるでしょうが、「教科書」の内容が通用する状況ばかりではないということは、過去に一時期存在した「想定外?」の(分散効果が効かない)市場環境でもわかるかと思います。
運用業界では、アロケーションを操作することが「無意味」であると認めてしまうと、仕事がなくなってしまうので、いろんな専門用語やセールストークを利用して「意味」があるように見えるように努力はしていると思います。
はい!結論としては、重要な要素であるものの、「単純」に成果を期待できる有力な手法は、現時点では存在しないということです。でも、資産運用のプロを自認するかた(?)であれば、顧客(もっとも、ニーズはことなるでしょうが)に対し、代替的なソリューションを提供することが必要ではないかと思います。
2022年11月21日
確定拠出年金(その3)

かなり期間があいてしまいましたが、確定拠出年金シリーズ第3弾です。これまでの投稿のURLは以下の通りです。
http://schole.chesuto.jp/e1378542.html
http://schole.chesuto.jp/e1380879.html
トップの画像はご存知のかたも多いでしょうが、「iDeCo」ですね。以前の投稿で企業型と個人型があると言及しましたが、こちらは個人型の確定拠出年金になります。個人事業主やフリーランス、主婦や主夫のかたでも利用可能です。
まずは管轄の厚生労働省の公式サイトにあるURLを記載します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html
私は確定拠出年金自体は20年以上前の30歳のころに運用開始しました。転職や脱サラでポータブルしました。最後に脱サラした6年前に再度個人型に変更し、現時点では資産は3倍以上になっております。
鹿児島銀行を窓口にした場合は、東京海上が管理運営機関の様です。
モーニングスター社のサイトでもラインナップを確認できます(以下URL参照)。
https://ideco.morningstar.co.jp/compare/0185.html
一般には、ネット証券の方がファンドの品揃えは多いですが、インデックス中心に運用される方の場合はあまり多くても意味がないかと思われます。
次回はファンド選択とウェイトのかけ方について書こうかと思います。
2021年06月21日
株式会社の話

新型コロナの変異株が話題になってますね。「株」とは細菌やウイルス、植物でも使われる言葉です。一定のまとまりとか同一系統という意味に使われますが、このような意味の発祥は木の「切り株」のようです。昔の商業組合で利権を共有する「株仲間」や武士の身分にも「御家人株」などといって売買の対象となったものもあります。
もちろん「株式」の意味でも使われます。株式とは会社法では「株式会社における社員の地位」となり文字通り読むと株式保有者が社員と言う意味にもとれますが、一般的には株主としての権利を意味します。株式を購入して株主になれば議決権の行使や配当をもらえたりしますね。株式会社によっては株主優待の制度を設けているところもあります。
日本の会社はほとんど株式会社の形式をとっていると言われています。会社法の改正でかつての有限会社は設立できなくなりましたが、他には合同会社、合名会社、合資会社などもあり、中でも合同会社の設立は増えているようです。
株式会社には上場会社と非上場会社がありますが、前者は全体の1%程度でほとんどの会社は非上場です。上場会社の数に関しては以下のURLを参考にしてください。
https://www.jpx.co.jp/listing/co/index.html
そして上場とは市場に株式を公開することですね。これにより市場からの資金調達が可能となります。これについては以前ブログで投稿したので以下にURLを記載します。
http://schole.chesuto.jp/e1381152.html
上場にはもちろんデメリットはあり、その実力があってもあえて上場しない会社もありますが、上場企業と言う事で知名度が上がり、従業員のリクルートに有利となったりします。一般には非上場より上場企業の方が給与水準が高く福利厚生が充実していたりします。上場をする際に株価が上昇するケースが多くあるので将来性を見て先物買いをするベンチャーキャピタルや個人投資家もいます。非上場会社でも将来の上場に備えて社員持ち株会の制度を設けたり、有望な社員に特定の価格で株式を購入できる権利であるストックオプションを付与するところもあります。
非上場株の話はまた思いついたら書こうと思いますが、本日はこの辺で。
2019年10月26日
REIT

みなさんREITってご存知でしょうか?
Real Estate Investment Trustの略で、日本語では「不動産投資信託」となります。
投資信託とは少額(一万円くらいから)でも分散投資を可能にする金融商品です。
以前は、証券会社でしか購入できませんでしたが、亡き橋本元首相時代の金融自由化(要するに本業が立ち行かなくなった銀行の救済が目的?)以降は銀行でも購入可能にはなりましたが、当時は所詮はリスク商品には素人の銀行マンが不用意に顧客に売りつけたため、トラブルが多発して、結果として顧客保護のために金商法ができました。でも未だに営業の現場では遵守されていないような気がします。
実は、REITが出来たころ私は投資信託委託会社のアナリスト(いわゆるバイサイド)をしていました。
当時は30代の中堅で若手やベテランがやらないことを引き受ける「スキマ産業」的な立場にいたので
結果的に毎月、設定したREITに関連したレポートを書く仕事を担当していました。
株式投信や債券投信とは若干リスク特性が異なるため、資産クラス間の分散投資先のひとつとして脚光を浴びてました。金利に対する感応度は比較的高いですね。
先日、鹿児島市内の住宅街を仕事で歩いていたら、空き家を多数発見しました。住宅街ではなくて天文館のような繁華街でも空きテナントが目立ちます。もっとも繁華街に関しては鹿児島中央駅の開発の影響かもしれません。
日本全体でも人口は減っていますしもちろん鹿児島でもそうです。
経済学の基礎概念に「需要」と「供給」というものがあります。供給はともかく需要は人口が減れば減少しても当然ですね。
もっとも、経済の活性化(?)のために、一人一人がもっと消費してもっと働けば別かもですが。
タイトルのREITについては私などより専門家が詳細に説明したものがググれば出てくると思うのであえて細かくはは書きません。
一番伝えたいと思っているのは、その投資対象の実体は何でしょうか?一体何に投資しているのでしょうか?ということをよく考えることが大事であるとということです。広告のキャッチコピーや都合のいいことしか書いてない営業資料、金融マンの説明を鵜呑みにしないことが重要ですね。最後に当たり前の話ですが、よく言われる「命の次に大事なお金」を他人の判断に任せていいのでしょうか?
寝起きに書いたのでまだ脳が起きていないような気がします。内容や誤字脱字等、要修正箇所を見つけたら随時…
2019年10月21日
バリュー投資
以前、投資のスタイルに関してやグロース(成長株)投資について投稿したことがありました。ご参考までにまずは以下にURLを記します。
http://schole.chesuto.jp/e1721358.html
http://schole.chesuto.jp/e1380312.html
ちなみに私はスタイルはバリュー投資です。大儲けはしたことありませんが、損したことも一度もないです。グロースの成長株投資に対して割安株投資という表現もされます。
バリュー投資で有名なのはバークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェット氏と同氏のコロンビア大学在学時の師で一時期上司でもあったベンジャミン・グレアム氏ですね。グレアム氏は「賢明なる投資家」という著作でも有名で私も読んだことがあります。
バリューとは value つまり価値ということなので、その投資対象の投資価値を何らかの基準で推計して判断を行うものです。
判断の材料として株式の場合、株価に対する配当や利益の水準などを利用することは多いですが、かつてはブランド価値やEBITDAなどを計算して利用するケースもあり様々です。
具体的には「バリュー投資」といったキーワードで検索すればいろいろ手法が見つかるかと思います。
私の場合は全ての上場銘柄を流動性を含めた複数の判断基準でスクリーニングして100銘柄位に絞ってからひとつひとつ事業内容や財務諸表を確認するという作業を行います。
もっとも、利用する基準は少なくとも計算の内容の意味を理解してご自身で合ったものを利用するのがいいかと考えていますが、中には無茶な計算するものもありました。
インターネットバブルと言われていた時期に、私は社内でもコンピュータに詳しいほうという安易な理由でネット関連銘柄の担当アナリストになった時期がありました。当時でも玉石混交で数年で消えていった企業も多くありましたし、事業内容はインターネットとは関係ないのに社名に「ネット」という文字があるだけで株価が上昇した会社もありました。
当時のネット銘柄は通常のバリュー投資の判断基準でがかなり割高な評価しかできなかったのですが、どこかの証券会社のアナリストが提唱した株価をPV(ページビュー)で割るというものがあり、説明材料に使われていたこともありますが、結果は散々でした。
ネットバブルの時はウォーレン・バフェット氏はほとんどそういった銘柄に投資してなかったそうですが、インタビューでなぜネット銘柄を買わないのかと質問された時「事業内容が理解できないものには投資しない」との回答だったということです。
私もかつて顧客にも「ご自身で理解ができないならやめておいたほうがいいですよ」とアドバイスしたことも多々ありました。
もちろんそれはバリュー投資に限った話ではなくて全て当てはまるのではと考えています。
最後ですが、ネットバブルの時の上司とのやりとりを投稿したことがあったのでこちらもURLを記します。
http://schole.chesuto.jp/e1379530.html
http://schole.chesuto.jp/e1721358.html
http://schole.chesuto.jp/e1380312.html
ちなみに私はスタイルはバリュー投資です。大儲けはしたことありませんが、損したことも一度もないです。グロースの成長株投資に対して割安株投資という表現もされます。
バリュー投資で有名なのはバークシャー・ハサウェイのウォーレン・バフェット氏と同氏のコロンビア大学在学時の師で一時期上司でもあったベンジャミン・グレアム氏ですね。グレアム氏は「賢明なる投資家」という著作でも有名で私も読んだことがあります。
バリューとは value つまり価値ということなので、その投資対象の投資価値を何らかの基準で推計して判断を行うものです。
判断の材料として株式の場合、株価に対する配当や利益の水準などを利用することは多いですが、かつてはブランド価値やEBITDAなどを計算して利用するケースもあり様々です。
具体的には「バリュー投資」といったキーワードで検索すればいろいろ手法が見つかるかと思います。
私の場合は全ての上場銘柄を流動性を含めた複数の判断基準でスクリーニングして100銘柄位に絞ってからひとつひとつ事業内容や財務諸表を確認するという作業を行います。
もっとも、利用する基準は少なくとも計算の内容の意味を理解してご自身で合ったものを利用するのがいいかと考えていますが、中には無茶な計算するものもありました。
インターネットバブルと言われていた時期に、私は社内でもコンピュータに詳しいほうという安易な理由でネット関連銘柄の担当アナリストになった時期がありました。当時でも玉石混交で数年で消えていった企業も多くありましたし、事業内容はインターネットとは関係ないのに社名に「ネット」という文字があるだけで株価が上昇した会社もありました。
当時のネット銘柄は通常のバリュー投資の判断基準でがかなり割高な評価しかできなかったのですが、どこかの証券会社のアナリストが提唱した株価をPV(ページビュー)で割るというものがあり、説明材料に使われていたこともありますが、結果は散々でした。
ネットバブルの時はウォーレン・バフェット氏はほとんどそういった銘柄に投資してなかったそうですが、インタビューでなぜネット銘柄を買わないのかと質問された時「事業内容が理解できないものには投資しない」との回答だったということです。
私もかつて顧客にも「ご自身で理解ができないならやめておいたほうがいいですよ」とアドバイスしたことも多々ありました。
もちろんそれはバリュー投資に限った話ではなくて全て当てはまるのではと考えています。
最後ですが、ネットバブルの時の上司とのやりとりを投稿したことがあったのでこちらもURLを記します。
http://schole.chesuto.jp/e1379530.html
2017年02月26日
音楽と株式市場

私は音楽は好きで楽器も弾きますが、所詮は素人で要は宴会芸レベルです。
実は、音楽よりはお酒のほうが好きなので、楽器を練習する時間があるなら、お酒を飲んで上手なかたの演奏を聴いたほうが良いとも考えています。
新入社員で投資信託の運用会社に入ったころ、大学の友人の影響でいわゆるテクニカル分析をかじりました。
以前、ブログでテクニカル分析について振り返ってみました。当該URLは以下の通りです。
http://schole.chesuto.jp/e1713112.html
自分なりにはいろいろ研究し、独自の分析手法も考案しましたが、10年くらいのバックテストをすると
勝率が50%に収束したのと、なんとなく感覚的に自分には合っていない手法だと判断し、
それ以上は研究するのはやめました。
しかし、ある時音楽と数学に親和性があると聞いたことがきっかけである手法をやろうかと思いました。
つまり、株価の動きを楽譜にあるメロディラインと認識し、メロディが存在するなら、
音階、和声、リズムといったものもおそらく認識でき、結果的に予定調和というものが存在するなら、
音楽理論で株価の推移を捉えられないかと思いました。
しかし、指数や個別銘柄で当てはめてみてもなかなかうまくいきませんでした。
音程がオクターブ上がると周波数は倍になります。
しかし、短期間で倍になる株価というのは、少数派です。
もっとも、対数変換でもすればよかったかもしれませんが、
私は努力するのが基本的に嫌いなのであきらめました。
音楽理論についてもちょっとかじっただけなので、それも問題かもしれません。
どなたかやってみませんかね。
株価の動きがランダムウォークであれば、現代音楽で解釈できるかもしれません。
もしくはフリージャズ?