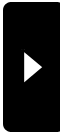2023年07月20日
FX?

自身が理解できないことを否定する傾向があるひとが散見されます。対象が胡散臭いというケースもままありますが、単に当人の理解力が不足しているということも多くあります。ちなみに、私は理解できないことは肯定も否定もせず、理解不能という分類にしておくことにしています。一時期、業務上、為替の予測のレポートをいやいや書かされていたことがありました。不幸中の幸いでドルとユーロだけでしたが。とりあえずファンダメンタルズを踏まえた、政治と経済のシナリオ分析、そして確率統計を使っていました。
予測(予想?予め想う?)は誰でもできますが、有意な水準で的中するのは、プロと言われるひとでも現実問題として困難です。そして株や金利以上に為替の予測は難しいと思っています。まあ、上がるか下がるか二つにひとつなので簡単だと思われるひともいるかもしれません。もっとも、そういう単純な発想も否定はしませんが。
一般に経済的に強い国の通貨は強く、金利水準も高いことから、通貨変動において、金利差に注目したりします。もっとも、それだけで儲かることもありますが、それほど単純でもありません。変動要因が多いほか、先の変化をどこまで市場が織り込んでるかはなかなか読むのが難しいからです。
吉祥寺にあった会員制(?)クラブで飲んでたら、支配人が寄ってきて、「豪ドルはこれからどうですかね?」と聞かれたことがあります。正直、仕事のこと考えたくないのでこういうところで飲んでるのにと不満でしたので、「よく考えてみてください。仮に私の予測が7、8割程度当たるとしましょう。そんな人間がサラリーマンやっていると思いますか?FXなどに手を出すより本業に専念されたほうが良いかと思いますよ」と答えました。その支配人はその後、近くの比較的廉価なキャバクラの支配人に転職されました。
FXで大儲けした主婦などが注目されますが、まあ確率論的にはありえることなので、特に驚きはしません。ゼロサムゲームでは、一握りの勝者の陰に大多数の敗者が存在するのではとも思います。もっとも、知り合いでFXで生計をたてている方もいますが、そういうかたは予測が困難ということを熟知されてます。勝つことよりも負けないこと、つまりポジション・コントロール、結果としてリスク・コントロールが重要かと思われます。
FXは先物取引と同様にレバレッジが存在しますので、安易に始めるのは危険かもしれません。
次はSFXかな?
2023年07月09日
首にロザリオ?チャーチスト!

大学生の時、私がある意味、影響を受けた友人が一人います。非常にクレバーな人物でした。彼は小学生の時から株式の勉強をして、高校生の時に株式取引を始め、株式投資で儲けたお金で大学の学費を捻出したり、高級車を購入したりしていました。その投資スタイルはいわゆるチャート分析もしくはテクニカル分析を踏まえたシステムトレードでした。世間一般で出回っているテクニカル分析を単に利用するだけではなく、独自に開発したものをプログラム化して自動的に取引を行うというものです。最近だとFXで同様のことを行っている人やその投資手法を販売している会社も多く見受けられます。
チャートとは元々は海図という意味ですが、株式投資の世界では、株価などの数値情報をグラフで表現したもののことです。グラフというのは何かを人に伝えるには便利なのですが、「百聞は一見にしかず」とはいうものの、人間は視覚情報にだまされることが多いので、わかりやすいのではなくて、わかったような気がしやすいというのが現実的だと考えています。
チャート分析の代表格は、移動平均法やエリオット波動理論、ギャン理論といったもので、日本のものだと酒田五法や一目均衡表などがあります。ちなみに日本では、江戸時代の米相場の時代からチャート(?)分析はあったようで、この分野の歴史は西欧より古いようです。
チャート分析とテクニカル分析は、ほぼ同意義の言葉として流通している感はありますが、グラフ化を必ずしも必要としない点では、テクニカル分析の方が広義であると考えられます。共通している原理というか基礎となる認識は、「全ての情報は価格に反映されている」、「市場の動きも自然の摂理に従う」、「歴史は繰り返す。なぜなら人間は歴史から学ばないから」といったところに集約されるかと思います。なんとなくわかったような気もしますが、私はあまり熟考したことないので真偽のほどは不明です。
私は業務上でファンダメンタル、テクニカル、クオンツなどの分析手法をかじりましたが、どれが優れていてどれが劣っているなどとは考えてはいません。なぜならいずれも様々な環境下において有意の確率で成果が期待できるものはほとんど存在していないという現実からです。もっとも、仮にそういったものが存在していたとしても、それを知る人がほかの人に教える動機付けが考えにくく、世間に広まるのも希だと思いますし、また仮にそれが広まったとしても、同じ行動をとるひとが増えるため、その手法の有効性は低下するかとも考えられます。
話をテクニカル分析に戻すと、大きく分けて2種類のタイプが存在しますトレンドフォロー型とオシレーター系と言われるものです。前者は、価格変動のトレンドなるもに追従するということですが、トレンドという言葉も曖昧で厳密な定義が難しいものの、この手法は乱暴な表現をすれば上がり始めたら買って、下がり始めたら売るといったものです。一方、オシレーター系というのは市場の過熱感や過冷感(?)を、何らかの数値で表現し、市場の潮目を察知することを目的にしています。市場はトレンドが形成する過程か、方向性の向きが変わる時点のどちらかに位置する(これも人間の勝手な認識?)ために、この二つの手法のどちらかは当たるという仕組みではあります。しかし、トレンドとは、現実的には後講釈であることが多いですし、事前どころかその時点でも現状がどちらになるのか認識は困難なので、やはり理論的背景よりは感性が重要なのかもしれません。考えるより感じろ、信じろということかもしれません。
冒頭に書いた友人に、大学卒業後数年したころ、兜町か茅場町あたりでばったり会ったことがあります。彼は当時、日本テクニカルアナリスト協会という団体の会員で、その会合で使われた資料を見せてくれました。その資料にはアンモナイトの化石の写真が掲載されていて、アンモナイトの渦巻きの縞の比率と株価変動の比率の比較や、黄金率やフィボナッチ数列について書かれてありました。会員になるには結構難しい試験を突破する必要があるようでした。私は努力するのは苦手なので諦めました。
2023年06月30日
ファイナンシャル・コメディアンズ協会?

私の高校の同級生がファイナンシャル・プランナーの事務所を山口県の柳井市で運営しています。
私も一時期、東京と地元でFP事務所をやろうかと考えたことはありますが、専門分野が資産運用だけでかなり偏っているので断念しました。FPの資格は、所属していた会社の昇格要件だったため取得はしましたが、FPのカバーエリアは広く、法律や制度変更などを継続的にフォローするのもズボラな私には向いていないとも思いました。
以前、FP協会ならぬFC、金融ネタで笑いを取りながらリテラシー向上に資するファイナンシャル・コメディアン協会とか、投信ファン(不安?)倶楽部などどいったNPOを作ろうと思ったこともありましたが、メンバー集めるのも大変なのでやめておきました。
多くのFP事務所は、実態は保険の代理店のような印象を受けますが、そのFPの友人にとある相談をした際に、最初に聞かれたのは「どういう状態が自分が幸せと考えるのか?本当に何がしたいのか?」ということでした。それによってアドバイスすることは変わるということです。単にお金が欲しいとかということではなくて、何か目的があって手段としてお金が必要なのだとは思いますし、お金以外の手段もいろいろあるかとも思います。彼は私と違って人格者で、ひとの話をよく聞くタイプで信頼でき、知識も豊富なFPさんだと思っています。
組織に属した金融マンは、顧客より所属する会社の利益を優先して、適合性の原則に反しても手数料の高い商品を勧めるするきらいもあります。まあ人は自由意思(そんなものが存在するのかは疑問)よりも置かれている状況で行動が左右されるかとは思います。
脈絡のないこと(いつもか!)を書きましたが、最後にその友人の事務所のサイトのURLを載せておきます、
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/
2023年06月27日
オルタナ…哀愁のヨーロッパは…サンタナ

オルタナティブという言葉があります。よくオルタナと略されています。もちろん英語で、alternative です。形容詞っぽい雰囲気ですが、実は名詞で「二者拓一」とか「代理、代替」という意味です。オルタナティブ・ロックというジャンルがあるそうですが、私は聴いたことないのでどのようなものかは知りません。しかし通常のロックとは何らか異なるものかとは想像できます。プログレッシブ(進歩的もしくは前進的?)・ロックというのも昔流行りましたが…
ところで資産運用におけるオルタナティブとは、株式や債券といった有価証券などの伝統的な資産とは異なる投資対象ことです。代表格は不動産(REITなど)、貴金属や農産物等などの商品(現物、先物やコモディティファンド)のほか、新興国市場の有価証券、そしてヘッジファンドなどがあります。変わり種としては一時期、黒毛和牛に投資するものやベトナムのエビの養殖事業に投資するもの、デビュー前のアイドル、映画などの興業、ラブホテル(一応不動産ですが)に投資するファンドなども流行ったことがありました。最近では通貨(FXは投資ではなく投機?)なども当てはまるかもしれません。もっとも、こういった投資対象は今となっては伝統的ではなくとも一般的とはなりました。
なぜ、こういった代替的な投資対象が求められるように、そして提供されるようになったかというと、伝統的資産のみでは投資手法などに工夫を凝らしても限界があるからです。特に分散投資を行う理由としての、分散効果が働かなくる環境が、例外的とは言えなくなったという点も背景としてあります。
しかしながら、オルタナの中でもヘッジファンドはまだまだ市民権を得てはいないかと思われますヘッジは英語の hedge つまり「回避」という意味ですが、基本的な目的は下落リスクを回避し、絶対的なリターンを獲得するということです。海外では普通に利用されてはいますが、日本ではまだまだ富裕層向けの金融商品という感があります。ヘッジファンドにも様々な手法があり、お互いの相関も比較的低いため、投資手法が異なるヘッジファンドを組み合わせた、ファンド オブ ヘッジファンズというものもあります。ちなみにキング オブ キングス(チャンピオン by アリス)とは意味合いが異なります。最近は、いわゆるメガファンドではないものの、公募や私募の投資信託で手法としてヘッジファンドであるものも露出が多くなってきました。
ヘッジファンドの状況をウオッチするには、いくつかの指数が存在し、代表的な指数の情報サイトは以下のとおりです。
ヘッジファンド・リサーチ社
https://www.hedgefundresearch.com/mon_register/index.php?fuse=login&hi
ユーリカ・ヘッジ
http://www.eurekahedge.com/Indices
クレディ・スイス・ヘッジファンドインデックス
http://www.hedgeindex.com/hedgeindex/ja/indexoverview.aspx?cy=USD&indexname=HEDG
多くの場合、伝統的資産のロングオンリーに比べると、ヘッジファンドのほうがリスク・リターン特性が優れているケースがあります。もっとも、FXと同様、レバレッジが高く設定しているものでは大きなダウンサイドのリスクもあります。
またの機会に、ヘッジファンドの歴史や様々な手法について投稿しようかと考えています。
2023年02月06日
確定拠出年金

以前、年金のことに触れました。日本の年金制度が崩壊するかどうかは不確定ですが、世の中有り得ないと思われていたことが起こるのは珍しいことではありません。
タイトルの確定拠出年金は、従来の確定給付年金とは異なり、拠出金は確定してますが、結果は自分の運用判断次第で異なっていくるというものです。運用の実態としては、一定のラインアップから投資信託を自分で選ぶということで、実質的には似たようなタイプの変額保険も存在しています。
確定給付は給付が確定しているという意味ですが、給付を受けるころに制度が変わってしまうリスクは当然あるので、厳密には不確定だと思われます。確定拠出年金は、導入されて結構経ちますが、導入当時は米国の一般的な表現である401Kから、日本版401kと言われていました。英国を真似て導入されたNISAと同様に、欧米の制度を日本向けにアレンジしたものです。
日本での導入当時、私は国内証券系の投資信託の会社に在籍していたこともあり、企業年金部分が確定拠出年金に変更されたたために活用せざるを得ない状況でした。当時は品揃えも一般的なものばかりだったので、オーソドックスな配分で運用しました。同業の会社に転職した時も、移籍先の会社が確定拠出年金制度を導入していたので、具体的な商品は変更は必要なものの移管できました。もっとも、一度目の脱サラの時には半年程度の猶予期間の後に、国民年金基金に移管されるところだったので、会社勤めでなくても可能な個人型に変更しました。もちろん、数年前に大きな損失をだしたことからも言えるように、国(?)の運用能力を信用していないことが理由でした。
まだまだ選択可能な商品のラインアップは不満が残りますが、税制における優遇など、徐々に制度が改正されてきてなかなか使い勝手も良くなりました。以前は、企業年金制度があるような大企業しか導入されていませんでしたが、中小企業や個人事業主、主婦なども利用可能になりました。もっとも、運用に関する知識は習得必要なために、実質的にはまだまだそこがハードルになっているかもしれません。
今後は気が向いたときに、具体的なことも書こうと思っています。
それではまた(社会派ブロガー、ちきりんさんのそんじゃーね風に)
2023年01月30日
運を用いる?

以前、感動を「感じて動く」という意味で使ったと書きました。URLは以下のとおりです。
http://schole.chesuto.jp/e1376998.html
さきほど、ふと思い出したのは、高校生の時に受けた国語の授業で、担当教諭が盲導犬という言葉は、中国の人には通じないと言われていたことです。多くの言語は、主語の後に動詞が続き、動詞の後に目的語がくるので、盲導犬と書くと、「目が見えない人が犬を導く」か「目が見えない人が導く犬」という意味に取られるとのことでした。そのため、正確(?)には、導盲犬(ドウモウケン)と表現しないといけないと言われました。まあ、多くの言語には、倒置法が認められているので、そこまで考えなくてもいいのでは?というのが当時感じたことでした。
このブログでも紹介しました、山崎元先生の著書「ファンド・マネジメント」の序章には、「運用とは、運を用いると書きます」という表現があります。資産運用に関しては、一部の例外を除くと、まさにこれが当てはまるかと思われます。多くの場合、結果は確率論的であり、継続的に勝ち続けるのは可能であっても、かなりのレアケースであります。金融マンの商品説明や、投資信託のパンフレットなどに「プロがやる運用」のような表現を見かけることがありますが、現実的ではありません。資産運用に限らず、世の中には自称プロという人種が多く生存し、実質的にはなんちゃってレベルであることが多いのではと感じることがままあります。特にテレビに出てくるような(自称?)プロは、多いような気が以前はしていました。本当のプロフェッショナルは、一部の例外を除くと本業で多忙なため、テレビなどに出る暇がないケースが多いのではとは思いますが、いろいろ大人の事情もあるのでしょうか。ちなみに10年以上前にテレビを処分したので、最近はどうだかわかりません。もっとも、プロという表現が「お金を稼ぐ」という意味合いで使われているケースもあるので、その意味では間違ってはいないのかもしれません。
資産運用には、様々なスタイルがあります。以前、年金運用に関して、運用者や組み入れる投資商品の評価をする仕事をしていた時がありました。さまざまな手法について分析をしたことがありますが、どれもメリット、デメリットがあります。世の中で売れる金融商品は、一般的な意味でわかりやすいものが多く見受けられますが、わかったような気がしやすいだけなケースもままあります。成果を上げるための「いい商品」は仕組みが複雑であったり、理解するためにそれなりの素養を求められることが多くあるかと感じています。でも、そういう商品は「わかりやすい、売りやすい商品」ではないので、販売する側にとっては「いい商品」ではなく、結果的に品質の良くない粗悪品が出回り、高い品質のものを排除する、「悪貨は良貨を駆逐する」ことになっているのではとも思います。まあ、ラーメン屋などのように、好みは別にしてうまいかまずいかはっきりしやすいものは別ですが。でも粗悪品があるから、良い商品の価値も際立つので、粗悪品の存在意義もあるのかもしれません。
暇なときに、様々な投資手法、スタイルの特徴や、メリット・デメリットについて書いてみようかと考えていますが、前置きを書いて疲れたので今日のところはこれまでにします。
2023年01月24日
投資バカにつける薬

専門分野の資産運用に関することをいくつか投稿しております。もっとも、その場の思いつきで書いているのと、やや観念論的である点は承知しています。しかし、ブログは日記のようなもの(徒然草?)であって、テキストではないので特に体系だっている必要はないのかもしれません。自分で体系だって書くのもいいのかもしれませんが、既に先人がいらっしゃるのでそちらを紹介したほうが、時間の節約になるかと思います。
これまで資産運用に関する書籍で影響を受けたのは、いくつかあります。大学卒業して運用業界に入り、先輩に勧められて購入したのが、敬愛する山崎元先生の「ファンドマネジメント」です。内容についてはネタばれを避けますが、正直、衝撃的でした。現在はテレビなどで活躍されてもいるので、ご存知のかたも多いかと思います。当時はまだ知る人ぞ知る存在でしたが、文章や舌鋒も鋭いかただと感銘を受けました。10数年前、たまたま先生と共通の知り合いが数人いたこともあり、先生の同著書に影響を受け、指針としていますという内容のメッセージをスコッチで酔った勢いで送ったところ、友達申請の許可をいただいた上、私が不用意にも投げかけた考えに対しても、ご親切に返信をくださいました。話を戻しますが、この本の内容を理解するには、少なくとも証券アナリスト検定試験の1次レベル程度の知識(投資理論や数学、統計学)は必要です。運用業界を目指す学生さんなどは、結構クリアしてるケースもあるので、是非読んでみて欲しいと思っています。
本屋に並んでいる投資関連の多くは、インチキ本やトンデモ本が多く見受けられます。山崎先生は、専門家向けのものばかりではなく、一般のかた向けにも書籍を出されていて、割と人に勧めているものが以下の二つです。
「エコノミック恋愛術」 参考URL:http://toyokeizai.net/articles/-/1970
「投資バカにつける薬」 同上:http://fund.jugem.jp/?eid=101
もっとも、前者は経済理論や投資理論の説明が中心で、後者のほうが資産運用に関して、世間で勘違いされていたり、金融マンが顧客についている嘘(もっとも金融マン本人も嘘だと気づいていないかも?)などが書かれてあり、どちらかというと後者のほうが薬だけに金融マンに騙されないためには即効性があるかとは思います。余談ですが、大学生の時に読んだ、評論家の呉 智英氏の「バカにつける薬」という本もなかなか面白かったです。
本を買うの面倒だと思われる方むけには、先生のブログなどを以下に紹介しますので宜しければご覧下さい。
ブログ「王様の耳はロバの耳」 http://blog.goo.ne.jp/yamazaki_hajime
レポート&コラム「本音の投資教室」 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/market/opinion/fund/yamazaki/
2023年01月22日
年金漫画?

ずいぶん前ですが、facebookを見てましたら、どなたかがとあるブログを紹介してました。厚生労働省の年金制度考証に関する漫画について書かれたものでした。とりあえずネタバレを避けてURLを以下に記します。
http://pokonan.hatenablog.com/entry/2015/01/13/141330
これを見たとき、昔、とある地方公共団体が運営している競艇場が経営難になった際、若者を顧客として取り込むために、主人公の若者が競艇を通じて勝負というものを学び、仕事でも成功するという内容の漫画を作ったのを見たのを思い出しました。漫画はもともと世相を風刺するために生まれたような話を聞いたことがありますが、ちょっと情けないなあと思いました。
私は政府の能力に期待はしていないので最近のGPIFの運用成果はチェックしてません。この年金の漫画の内容の真意や真偽はともかく、まあ薄々勘付いて覚悟していてねということを醸し出しているのかもと思っていたら、あの老後に2000万円足りない問題がその後発覚しました。年金制度がいつごろ崩壊(制度変更?)するかどうかはわかりませんが、養育費を捻出したり、老後の生活を成り立たせるためには、文句を言っても始まらないので一層自助努力も必要なのではと考えています。
倹約して貯金するというのも必要でしょうが、デフレと言われて久しい環境の中でも、円安による輸入インフレで生活必需品がさりげなく値上がりしていたり、現在の政府の2%のインフレターゲット政策が継続的に実現する場合を仮定すると、貨幣価値は下がり、貯金では当然のことながら間に合わないことも多くの場合あるかと考えます。
私は現在、仕事としては関与してませんが、資産運用はマネーゲームであったり、一部の富裕層のために存在しているのではなくて、多くのかたが真剣に考える必要があると考えています。もっとも、働けなくてお金もなくなったら死ねばいいという選択肢もあるかもしれません。
資産運用のアドバイスを一般的な金融機関で受けるのは、これまでの経験や業界内の事情などから危険であるとは思っています。もっとも、既存の金融機関に全く関わらないのは困難にしても、騙されないためには人任せにせず、ご自分で批判精神を持って学ぶ必要があるかと思います。
うーん…前置きを書いていたら本論書くのが面倒になってきたので続きはまた今度…
2023年01月19日
分配金って?分けて配るお金…

以前、知人のご高齢のかたから電話があり、投資信託を勧められたのでどうしようか迷っていると相談を受けました。そのかたは会社経営に携わっていますが、投資には興味はそれほどなかったものの、メインバンクの紹介だったために無碍に断れず、話だけは聞かれたとのことでした。
商品名はあえて伏せますが、どんなセールストークだったのか聞いてみましたら、「アベノミクスで儲かります。分配金が毎月●●円でます」とのことでした。現場にいた訳でもないので、実際のところはわかりませんが、アベノミクスがどのようなもので、同政策の失敗を予想するのか成功を予想するのかは別にして、結果として何が起こるのかというシナリオを元に、商品性に絡めて説明がされたのか確認してみたら、そういう話はなかったとのことでした。もっとも、説明されても頭に入ってこなかっただけかもしれません。まあ、その商品性からは、結論として円安にベットするということが推測されましたが、それほどハイリスク商品でもなく、そのかたの立場としてメインバンクとの付き合いもあるでしょうから、損をしても構わない金額程度で購入するというのもあるものの、ご自分が理解できないものには、手をださないほうが良いかと思いますよと話しました。もっとも金商法上は、この金融マン、もしくはその販売会社の商品の売り方には問題はあると感じました。
ところで、セールストークにあった分配金とは、本来、投資信託の収益から受益者に分配されるものです。昔は、半年とか年に一度、運用成果が上がった時にされていました。銀行での窓口販売が解禁され、毎月分配のパイオニアとして有名な国際投信投資顧問のグローバル・ソブリンがメガ・ファンドとなって久しいですが、販売当初は業界内では、こんな馬鹿げた商品なんてと酷評されたものの、結果的に販売実績が上がったので、運用会社各社が一斉に毎月分配商品を作り、現在に至ります。運用(運を用いると書きます BY山崎元先生)は必ずしも成功するとは限りません。月間でマイナスの成果だった時も分配するというのは、単に元本を切り崩しているだけです。
私は毎月分配金については、どちらかというと朝三暮四的な感があるだけでなく、運用上は不合理な存在であると考えています。投資先進国(?)の欧米の運用業界関係者からも、日本はなんで分配しないといけないのか質問されたことはありますが、単に課税対象をつくりたいという大人の事情かもしれませんし、それを求める人(顧客側なのか販売側なのか?)がいるためかもしれません。結果として、その制度や商品は存在している訳です。
分配とは「分けて配る」と書くので、日本語として間違っている訳ではありませんが、誤解を招く表現ではあるので「毎月強制解約金」と表現すべきと考えており、以前山口県のブログサイトで書いたこともありました。一時期、毎月の分配金を基準価額で割って、分配金利回りという不届きなセールストークも存在していました。運用が失敗して基準価額が下がれば、利回りは計算上高まります。また、個別元本方式で、受益者が購入した時の基準価額から計算して、課税対象にするかどうかが分かれており、課税対象部分は「普通分配金」、元本を切り崩しているだけの部分は「特別分配金」と表現されていましたが、金融庁も現場で生じるトラブルを憂慮したのか、現在は後者は「元本払戻金」という名称となっています。でも、販売の現場はなかなか変わらないのかもしれません。
2023年01月15日
投資信託の販売手数料は何に対する対価なのでしょうか?

以下は12年前にUターンして、地元の銀行で働き始めた時に感じたことを、趣味人倶楽部の投信コミュニティに投稿した内容です。
=======================================================================
以前、投資信託の運用会社に在籍し、最近地元の銀行にUターン就職して、投信を含む資産運用サービスに従事している者です。運用会社にいた時から、販売手数料は顧客に対する、購入時の説明および購入後のアフターフォローに対する対価であると思っていました。
また、信託報酬の一部(場合によっては運用会社より多い比率)も販売会社である、証券会社や銀行に支払われます。全般的に、リスクの高い投信ほど、手数料も高くなっているような(ノーロードは対象外)気がしますが、最終的にリスクをとるのは受益者なので、投信自体のリスク水準は手数料の水準の直接的な説明にはならないと思われます(もっとも、説明に手間がかかるものが高い手数料であるのは分からないではないですが)。邪推ですが、顧客が損失をこうむった場合のクレームリスクがプレミアムとして含まれてるのでしょうか?
最後に、投信購入者のかたがたへの質問ですが、手数料に見合う(と思われるような)説明を受けられていますか?忌憚の無いご意見をお待ちしております。
=======================================================================
この投稿に対して、個人のかたや業界関係者からコメントをいただきましたが、販売手数料が安くても、信託報酬や別の名目で高い報酬をとっているものもあるのではとの指摘を受けたりしました。しかしながら、報酬の水準自体は重要な論点にしてません。運用会社でも販売会社でも報酬に見合うサービスを顧客に提供しているのかどうかが肝要かと考えてます。顧客がより経済合理性を追求すれば、本当のプロフェッショナルを雇うか、ネット証券やETFを利用するような2極化がおこるかと思われます。保険業界なども既にそのような兆候ですね。もっとも、知識はなくても可愛い女子販売員に説明らしきものをして欲しいという顧客もいるかもしれないですが…その場合は指名料とか発生しますね…不謹慎?