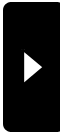2024年04月05日
リスクは危険ではなく…

大学卒業して最初に入った運用会社は、なかなかユニークな会社でした。親会社は元々、関西に本社がありましたが、私が入社する前に東京に本社を移したものの、やはり関西系のかたが多くいました。現在は合併して、みずほ証券となっています。いまだに口座がありますが、10年以上利用していません。
私が入社した頃のグループの企業文化(?)は、関西系だったからか、プロセスよりも結果重視という野武士集団でした。学歴や教養、知識、品性などよりも、結果を出せばいいというものでした。結果はもちろん生き残るためには重要なのですが、結果というのは偶然の要素も多くあります。もっとも、何もしなければ失敗もしないものの、結果も出ません。
新入社員の時に、当時会社で珍しいというか唯一の(?)インテリ先輩に教えられました。
先輩 「リスクとはなんだかわかるか?」
私 「危険のことですか?」
先輩 「直訳ではそうだが、不確実性のことさ。運用業界用語ではボラティリティだな。」
運用業界では、収益率の不確実性を表現するのに、一般的に標準偏差を使用します。標準偏差とは、データのバラツキ度合いを意味し、各データの平均との差の2乗の加重和(分散)の正の平方根です。この説明でわからないかたはググっていただければ幸いです。
リスクがなければリターンもないというのは極論ですが、多くの場合当てはまります。正確には超過収益にはリスクが存在するということです。確実に収益があがるような投資対象は、皆がこぞって投資するため、結果として収益率が低下します。不確実な部分がある投資対象は実行するかたが少なくなるためにチャンスも存在します。
本日、たまたま損害保険業界のかたと話をする機会があり、運用業界とは異なるリスクについて教えていただきました。生きていれば様々なリスクがありますね。生き延びるためには、様々なリスクに対し、ある程度ヘッジする必要もありますね。
そういえば、学生時代、パソコン用のCISCチップではなくて、ワークステーション向けにリスクチップというのがありました。スペルはRISCだったかな?SUNのスパークとか…命令セットが単純なために構造も単純で、結果として高速化が実現出来たようです。
2024年04月01日
ヘッジファンドのすすめ?

ヘッジファンドというのをご存知でしょうか?以前ブログに簡単な説明を書いたことがあるので該当URLをまずは記します。
http://schole.chesuto.jp/e1712441.html
マスコミなどで、金融市場を混乱させる要因として悪者扱いされることがたまにありますが、そもそもマスコミの情報の多くは、マスコミ関係者の無知や無恥、無教養、不勉強、業務怠慢などが原因(もしかしたら確信犯かも?)で誤った情報がタレ流しになっているので信用しない方が良いかと考えています。
アナリストという仕事をしていた時、5時くらいに起きて、NY市場をニュースでチェックし、通勤電車で日経新聞を読み、会社に着いてから一般紙、業界専門紙などを合わせて10紙程度読んでいた時期がありました。しかし、自分で裏をとったりすると、明らかな間違いとか、勘違い、誤解を招く表現などが散見されました。もっとも、今時はマスコミの情報を真に受ける人はあまりいないかもしれません。
個人のかたが分散投資するには投資信託が適しているかとは思います。しかし、いわゆるロングオンリー(買い待ち)の場合は、分散効果が働かないというケースもままあります。もっとも、投資信託自体が分散投資を目的としてはいますが、アセットクラスが同じであれば、同じ方向に動くケースが多いかとも思われます。
運用のプロと言われているひとたちでも、なかなか市場の方向性を安定的に当て続けるのは困難です。なので、市場の方向性を予想するのが無理だと思われたなら、ヘッジファンドを資産に組み入れることは有効な手段かと考えています。ヘッジファンドにも様々な手法がありますが、代表例としては、ロング・ショートとマーケットニュートラルというものがあります。
前者は名前のとおり、買いと売りを組み合わせるもので、対象は個別銘柄であったり指数先物であったりします。結果的に該当アセットクラスのエクスポージャーが低く、当然リスクも低くなります。もちろん、万能ではありませんが、市場のことがよくわからないのに、通常のロングの投信を所有するのはストレスの原因となり、本業に差し支える可能性があります。
次に後者のマーケットニュートラルですが、市場中立という意味で、基本的にエクスポージャーは0近辺となります。コントロールするエクスポージャーはネットの組み入れ比率であったり、ベータであったりします。前者よりもリスクは低くなることが多いです。収益の源泉は、個別銘柄のスペシフィックリターンであったり、ファクター(個別銘柄の収益に含まれる特定の共通要素)のリターンであったりします。
国内には多くの公募投資信託がありますが、モーニングスターなどでカテゴリー検索するとヘッジファンドはそれほどありません。通常の投資信託よりも収益の結果としては初心者向けであると考えていますが、販売側に理解力や説明力が不足している問題があるのかなと思います。しかし、わかりやすいものが良いものとは限りませんね。以前は富裕層向けと考えられていたヘッジファンドもここ数年は徐々に浸透してきている気がします。
最後ですが、ヘッジファンドを扱うFPさんにも会ったことはありますが、ほぼ専門知識のない売り子(ブローカー)でしかないかたも散見されました。まあそういうのに騙されるのも自己責任だとは思います。
2024年03月14日
実体のない煙

私が金融(投資信託委託および投資顧問、銀行)業界から足を洗ったのは、きっかけがありました。仕事自体の存在意義に疑問を思ったからです。どうも情報の非対称性から顧客に正確な情報を伝えきれていないか、もしくは金融マン自身が正しい情報を知らないという感がありました。
若い頃は、わからないことが多すぎて、それがわかるようになるように専門書を読んだり、専門家に聞いたりしましたが、やればやるほど疑問のほうが増えてきました。それでも、やれば理解できるようになると考えていました。
ある時、後輩から勧められた本で愕然としました。日本語版が出る数年前に、米国で出版されたものでしたが、著者はナシーム・ニコラス・タレブ氏というかたで、タイトルは「まぐれ」で副題が「投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか」というものです。詳しい内容はネタバレを避けますが、要はプロとか専門家と言われる人達が、実際にできることの限界を示したものです。以下に楽天BOOKSのリンクを貼っておきます。
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】まぐれ [ ナシーム・ニコラス・タレブ ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1226%2f9784478001226.jpg%3f_ex%3d240x240&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1226%2f9784478001226.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】まぐれ [ ナシーム・ニコラス・タレブ ] |
ちなみに、その後、同氏は「ブラック・スワン」という著作も出されましたが、素材は若干異なるものの、内容はほぼ一緒であったような気がします。割と専門性が高く、金融知識や統計学の素養がないと理解しにくい内容であったにも関わらず、当時のビジネス本でベストセラーになってびっくりしました。そしてその後、「ブラック・スワン」という映画が封切られましたが、まったく関係ございません。著書に関しては、上下巻ですが、念のためリンクを貼っておきます。
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】ブラック・スワン(上) [ ナシーム・ニコラス・タレブ ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1257%2f9784478001257.jpg%3f_ex%3d240x240&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1257%2f9784478001257.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】ブラック・スワン(上) [ ナシーム・ニコラス・タレブ ] |
![【楽天ブックスならいつでも送料無料】ブラック・スワン(下) [ ナシーム・ニコラス・タレブ ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8881%2f9784478008881.jpg%3f_ex%3d240x240&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f8881%2f9784478008881.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】ブラック・スワン(下) [ ナシーム・ニコラス・タレブ ] |
また、これは小説ですが、ノア・ゴードン氏の千年医師物語シリーズ(たしか3部作)の第一弾の「ペルシアの彼方へ」でも考えさせられました。内容の大枠としては、孤児であった主人公が、当時インチキとされていた旅回りの外科医(内科医は認められていましたが)に拾われて、最後はペルシアで医術を学ぶいうものでした。師匠の外科医が亡くなった時に、主人公が墓碑に師匠本人がよく言っていた、「私は実体のない煙を売った」と刻んでもらったことが印象に残っています。もっとも、エンターテイメントとしても十分楽しめました。そして、実は映画化されたようです。文庫版・上下巻で既に絶版のようですが、中古が出回っているので、こちらも楽天BOOKSのリンクを貼ります。
![メール便送料無料!【中古】 ペルシアの彼方へ 千年医師物語 (上) / ノア ゴードン [文庫]【メ...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fcomicset%2fcabinet%2ffolder76%2f4042881017.jpg%3f_ex%3d240x240&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fcomicset%2fcabinet%2ffolder76%2f4042881017.jpg%3f_ex%3d80x80) メール便送料無料!【中古】 ペルシアの彼方へ 千年医師物語 (上) / ノア ゴードン [文庫]【メ... |
![メール便送料無料!【中古】 ペルシアの彼方へ 下 / ノア ゴードン / 角川書店 [文庫]【メール...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fcomicset%2fcabinet%2fno_image.jpg%3f_ex%3d240x240&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fcomicset%2fcabinet%2fno_image.jpg%3f_ex%3d80x80) メール便送料無料!【中古】 ペルシアの彼方へ 下 / ノア ゴードン / 角川書店 [文庫]【メール... |
実体のある、つまり何らかの形で誰か(通常は顧客や同僚)の役に立つ仕事をしたいものです。
2024年01月08日
スタイリッシュ?

私は子供の頃からスポーツと同様にファッションに興味持ったことはありません。入学した大学が、世間では比較的お洒落な大学というイメージがあったようで、ある時、郷里の母からお米などが送られてきたのですが、ダンボール箱の中にメンズノンノという雑誌が一緒に入ってました。当時は大沢たかおさんや松雪なんとかさんがモデルで出てました。まあ、母としてはファッションに興味のない息子へのアドバイスのつもりだったのでしょうが、メンズノンノって高校生向けだったような気がします。しかしながら、実際の行動は変わらず、甚平に雪駄で渋谷のキャンパスに行ったことも何度かあります。でも、たしかに私の周りにはお洒落でスタイリッシュな学生が多くいたようにも思えます。
ところで、以前も書いたことありますが、資産運用にはスタイルと言われれるものがあります。まあ、投資手法という意味合いのほうがわかりやすいでしょうが、例えば、株式でいうと、成長期待の高い小型株を探すとか、安定していて割安な株、配当利回りの高い株などを選別するというのもあります。また、初期段階の投資候補銘柄群をユニバースという表現で言うこともあります。そのユニバースから、特定の条件によって機械的に選別することをスクリーニングと言ったりします。
スタイルには、以前も書いた、バリュー(割安株)、グロース(成長株)、スモールキャップ(小型株)などの分類の他にも様々なものがあり、割とメジャーなものとしてクオンツ(定量的手法、システム運用も含まれるかな?)やボトムアップ(リサーチによって個別銘柄を探す)、トップダウン(経済分析等による業種やテーマの選択等)などがあります。セクターローテーションやアノマリーに注目したりします。また、アクティブやパッシブという分類もあり、前者は何らかの手法によってベンチマークを上回る収益を目指し、後者はインデックス運用に代表されるようにベンチマークとの連動性を目的とするものや、フォーミュラ運用といって機械的なルールで決める(システム運用にも似てますし、アクティブな面もあるので体系的な分類にはならないケースもあります)ものもあります。
定量分析は分析手法を教科書的に勉強すればだれでもできますが、定性分析はそれなりに素養や訓練を必要とするような気がします。様々なスタイルがあり、どれが優れているとは一概には言えません。しかし、定性分析においては、まずは投資哲学というものが存在し、その哲学の元に投資目的が設定され、スタイルが選択されます。そして一番重要なのは、それを実現するためのリソースがあるかということと、哲学から実務に流れる一貫性があるかどうかということです。
よく、「プロが運用します」とか、ひどい時には「頑張ります」という説明があります。前者については、本当にプロフェッショナルなかたはほんのひと握りであるという現実がありますし、後者は単に「僕を男にしてください」と言ってるのとたいして変わらないような気がします。
多種多様なファンドのスタイルから選ぶには、このような内容について共感できるかどうかということが大切なのではないでしょうか?もっとも、互いに相関の低い、スタイルを分散させるということもリスクリターン特性を改善することにもなります。金融マンに勧められた時に、この観点で質問するといいかもと思います。そうしないと単に手数料や信託報酬の高いものを勧められるかもしれません。適合性の原則違反で…
2024年01月05日
外貨建資産を組み入れた投信の時価評価

先日ヘッジ目的のために外貨建て資産を持つということを書きましたが、書き忘れた余談(?)があったので追加します。
外貨建て資産はその名のとおり、外国通貨建てですね。当然、為替が絡んできます。一般的な国内の公募投信の場合、基準価額は円表記ですね。もちろん、外貨建て資産の時価に為替で円建てに変換している訳です。
外国の市場とは時差がありますので通常、前日のもっとも近い営業日の現地の時価を、日本国内当日の為替で評価します。前者については、例外としてファンド・オブ・ファンズや外国籍投信を組み入れたものの場合、現地市場の時価がずれることもあります。後者については投資信託協会が採用している為替を利用しますが、実は、三菱東京UFG銀行が午前10~11時くらいに発表している為替をと同じものです(以下URL)。Excell形式でもダウンロードが可能なので便利です。
http://www.bk.mufg.jp/gdocs/kinri/list_j/kinri/kawase.html
為替は通常、売買によって値段に差(スプレッド)があり、T.T.S. と T.T.B.と言われます。投信の評価に使用する為替は、T.T.M.と言われ、T.T.S.とT.T.B.の仲値になります。
このように、該当する外貨建て資産を組み入れた投信の時価評価方法について知っていれば、当日の午前中には騰落率をおおまかには予測できます。もっとも、ベンチマークに対してアクティブリスク(もしくはトラッキングエラー)が高いケースではその限りではありません。
ちょっとマニアックなものとしては、外貨建て資産を組み入れた円建ての外国籍投信の場合は、WM/Reutersのレートが利用されていることが多いです。グローバルな株価指数を提供しているMSCIなども、円換算にこのレートを利用しています。
2024年01月02日
外貨建て資産でヘッジ?

最近は多少円高に戻りましたが、少し前まで150円台まで円安でしたね。政府はインフレターゲット政策をやってましたが、輸入インフレもまたじわじわと起こっているような気もします。物価が上昇しても、賃金の上昇がそれ以上に起きなければ、実質的に収入が減るだけでなく、将来のためにせっせと貯蓄しても、インフレ率分だけ目減りしていく訳です。
地元の銀行にUターン就職した際、一時期ですが投資信託の販売にも携わっておりました。入行前に一通り商品のラインアップはリサーチしており、銀行の顧客属性から、適合性の原則の中でどれを勧めるべきか考えたところ、取り扱いのあった30数本中2,3本しか見当たりませんでした。ある時、とある事業会社の経営者のところに営業に行きました。基本姿勢として、「この商品が儲かりますよ」というセールストークはしませんでした。というかそれをやったら金商法違反になります。まずは、その会社の事業内容をお聞きした上で、為替変動による影響を考慮しました。例えば、輸出などをしていなくても、仮に円安になった場合に海外から仕入れる原材料が高騰して収益が圧迫される可能性などです。そして、外貨建ての投資信託などをある程度持っていたら、いくらかはヘッジが可能となるということなどを説明しました。最近は、コモディティ関連のファンドもありますのでそちらを選択するという手もあります。もっとも、単純に儲け話が好きな顧客もいますので、その場合は、商品性、特にリスクを十分説明する必要もあります。
以前も書きましたが、資産運用は富裕層のためだけに存在している訳ではありません。儲けるというよりも、今後はインフレによる通貨価値の下落に備えるために必要不可欠かと考えています。年金も以前から言われているように不安ですね。政府はどうやら自らではなく、国民にリスクを転嫁したいような気もしますし、FXなどされないかたも、為替変動が大きく生活に影響を与えてくるようになるかと思いますので、全く考えないわけにはいきません。
そういえば、為替リスクを取りたくないために、日本株を選択するかたもいらっしゃるようですが、日本株は全体として為替の感応度が割とありますので、円建て資産だからといって実質的には為替リスクがないとは言えません。私は、10年以上前に運用会社を辞めた時に、会社で加入していた企業型の確定拠出年金を個人型に切り替えました。基本的に円安にベットするポートフォリオにしていたので今のところ運用成果は良好ですが、たまにはリバランスしようかと考えています。
2023年12月30日
投機(博打?)と投資の違い

唐突ですが、パチンコは3回しかやったことがないです。大学生のころ帰省したら、今は亡き父が「お前はパチンコやったことあるか?」と聞いてきたので「ないよ」と答えたら、「20歳過ぎてパチンコもやったことないのか!それはイカンな!」と言い、無理やりパチンコ屋に連れて行かれました。
そしてビギナーズラックで2万円くらい勝ちました。東京に戻ってやってみたら5千円勝ちました。3回目に5百円負けたのでそれ以降はやっていません。
基本的に博打といわれるものには今のところ、興味がありません。博打に使うお金があったらお酒飲んだ方が良いと思っています。もっとも、仕事以外で個人でも株式や投資信託などへの投資経験はありますし、確定拠出年金(個人型)の運用指図もやっています。
では、博打と投資とは何が違うのだろうかと考えたことがあります。世間一般で言われる表現では、投機(博打?)と投資の相違ということになります。
短期的なのが投機で、長期的なのが投資と言われたり、不確実性(リスク?)が高いのが投機、鉄板なのは投資という区別を見たことがありますが、具体的な期間や、リスク水準も不明で概念として大雑把過ぎるし、一概には言えないケースもあるかと思われます。
言葉というものは生き物で、本来の意味は一応あるものの、時代によって意味が変化したり、マスコミの影響で誤った使い方が一般化(ハッカーやホームページなど)してしまうということがあります。
以下は私の勝手な解釈なので真偽のほどは不明です。
博打や投機は単にゼロサムゲームであり、それ自身では何ら付加価値を生まず、投資は何らかの形で世に価値を生むことを目的としているということです。もっとも、経済学では貨幣の流通速度なる概念があり、まあ昔からいう「金は天下の回りもの」なので、博打や投機で儲けたひとが、何か食べたり飲んだり買ったりすれば波及効果はあるということですが、その分損をした人もいるはずかと思われます。
投資もゼロサムゲーム的な面もあります。しかし、分かりやすくするために株式を例にとると、事業資金を提供する意味があります。上手くいくと社会全体の富を増やすこととなります。また、経営状態の悪い会社の株が下がった場合、買収されてリストラされるというケースがあります。そして状態が悪い場合は、何らかの方法で良くなるか、最悪の場合倒産するわけです。適者生存という考え方からは、状態が悪いものは存在する必要はないとも言えます。しかし良くなる可能性を視野に入れて割安な株を買うということは、その企業を応援するということにもなります。うまくいくと存在意義あるものの存在を助けたということになります。もっとも損をしたとしても、買う時点での売り手に対して流動性の機会を提供するという意義も、屁理屈かもしれませんがあるかと思われます。投資とは社会的に意義のある行為と思っています。もっとも上場していたり、上場を目指す企業の中には社会に害をなす可能性があるものも存在するかもしれません。
数ヶ月前に、とあるSNS経由で、ギャンブルのスマホサイトの運営に協力するとお金になるというMLMのようなビジネスの話の説明を受けました。説明自体も胡散臭さが漂っていて、いろいろ質問したところ、まあ先行者には利益があるかとも思われましたが、最終的に博打の手助けをするということが頭に引っかかったので加入はしませんでした。もっとも、以前も書きましたが、MLMという仕組み自体を否定するつもりはありません。
http://schole.chesuto.jp/e1381147.html
そういえば、昔、パチンコ業界の収益は北朝鮮に流れると聞いたことがあります。真偽のほどは未確認ですが、それが事実ならパチンコするひとは、金体制の応援をしているということなるのでしょうか?もっとも、私は国や人種という枠組みで偏見を持つのは避けておりますが、過去の実績を鑑みると根拠もなく信用するのは危険かなとは思います。
私は株式投資に関してはバリュースタイルです。大儲けもありませんが、損をしたことは一度もありません。以前、バリューとグローススタイルについてブログに書いたことがあります。
グロース:http://schole.chesuto.jp/e1380312.html
バリュー:http://schole.chesuto.jp/e1610742.html
2023年12月27日
株式上場(公開)は何のため?

以前、アナリストという仕事をしていたことは何度か書きました。
株式を市場に公開することは、昔は上場か店頭登録かの二つでしたが、マザーズやヘラクレスなのど新興企業向けの市場が立ち上がって以降に、店頭登録もJASDAQ上場という表現になり、その後、プライムやグロースといった区分に変わり株式公開より上場という表現のほうが一般的になってきたような気もします。
本来、株式会社という制度は、事業を行う際に出資者を募り、小口(?)の資金を集めて、事業資金とするということが目的で生まれましたが、最近は少額でも設立できてしまいますね。
株式を公開するときは、公募で新株を発行する場合と、もともとの株主(創業者やベンチャーキャピタル、従業員持株会など)の株式を売りに出す場合があります。後者は、資金需要があるというよりは、それまでの株主に利益をもたらすことが目的かと思われます。株式を公開すると、長期的な経営計画や業績を定期的(4半期とか)に公表することとなり、業績が悪化している時などは、その理由や対策などについてアナリスト達に質問攻めにあい、彼らを納得させうる回答ができないと、売りのレポートなどを書かれたり、株価が下がったりして散々な目にあいます。株価が下がると、場合によっては買収される危険性もあります。
通常、上場前には主幹事の証券会社や証券アナリスト協会などの主催で、機関投資家向けに企業説明会が行われることが多いです。
私が学卒で運用会社に入り、調査部門に配属されて、見習いアナリストとして初めて出た説明会が、とある製造業の公開前説明会でした。企業名はあえて伏せます。
公開の理由のところで、とあるアナリストが「公開によって獲得する資金はどのような使い方をされる予定でしょうか?」と質問したところ、回答が「銀行からの借金を返します」だったために、失笑を買ってました。
また、いわゆる同族企業の会社が公開することとなった時に「創業者の社長さんの息子さんが役員に入っているようですが、その合理的な理由を教えてください。単に家族だからということではないですよね」というイジワル(?)な質問をしているアナリストを見かけたこともあります。(もっともそれが仕事なのですが)
上場することが目標という会社が多いような気がしますが、問題は上場したあとのことのほうがより重要で、株式を公開すると、ある意味で公共的な扱いになるため、いろいろ面倒なことがあります。上場している会社の多くはIR(Investors Relations)担当の部署や担当者を置いてます。アナリストがどのように考え、彼らを満足させるにはどうすればいいかということを助言するために、元証券会社の人やアナリスト出身者を採用しているところも何社か見たことがあります。
最後に私が現在住む鹿児島県は上場企業は少ないです(以下URL)。
https://j-lic.com/prefectures/46
給与所得水準が全国的にも低いと言われますが、大企業の商業施設や工場などが誘致できればという考え方ももちろんあります。若者を地元につなぎとめる方法としても有効でしょう。また、地元の企業を成長させ、上場もさせるということも方法のひとつかもしれません。
私の友人にも上場を目指して起業した若者がいます。また、大学の先輩で在学中に公認会計士試験に合格して現在は上場のアドバイスをするコンサルタント企業を設立したかたもいます。鹿児島の経営者のみなさま、優秀な人材を確保するためにも上場を目指してみませんか?
以下URLは上場コンサンルタントの先輩を紹介している公式サイトです。ご参考まで。
https://www.slctg.co.jp/member
2023年12月25日
安いよ!安いよ!お買い得?

投資信託には基準価額というものがあります。株式の株価のようなものです。株式の場合は1株あたりの値段ですが、投資信託の場合は、基準口数(大抵は1万口)あたりの信託財産(純資産)です。
株式では、株価の絶対水準によって、値嵩株とかボロ株とか表現したりします。投資信託は、設定時に10,000円からスタートする場合が多いので、現時点の基準価額が1万円を割っていれば、設定時に購入したかたは損をしていることになります(もっとも、分配実績がある場合はその分をかさ上げする必要がありますが)。以前、証券マンなどの投信販売をしているかたが、「1万円を割っている投信は売りにくい」と言っているのを見聞きしました。世の中には、全くの不合理かつ馬鹿げている話が多くありますが、これもそのひとつです。つまり、基準価額の水準自体は情報としてほぼ意味はありません。私のブログと同様気のせいの類ですね。何かを判断するにはいろいろと比較したりしますが、基準価額という数値だけでは何も判断はしようがありません。もっとも、ファンド・オブ・ヘッジファンズのように絶対リターンを目指しているものはこの限りではありませんが…投信の良し悪しを判断するにはリスク・リターン特性などの定量分析と、運用哲学との実態の整合性などの定性分析が必要なことは以前、ブログに書いた事はあります。あとは、信託報酬の料率などのコスト面も重要ですが。
この「1万円を割っている投信は売りにくい」という話を、以前、在籍していた運用会社の営業会議で営業担当のかたが話してたので、思わず「じゃあ、証券会社ではなくて、ジャパネットた〇たに売ってもらいますかね。例えば、「設定時1万円だったこの投資信託、今ならなんと5千円!安い!しかも販売手数料はお客様のご負担となります!」とか言ってもらって」と発言したら、怒られました。
やや論点は変わりますが、過去の定量分析で単純に収益率が悪い場合でも、一貫したスタイルをとっているものは評価できる場合もあります。スタイル・ローテーションとも言われたりしますが、年金運用の手法の一つで、一定の期間成績(?)が悪かったものをあえて選択するという発想があり、似たようなものでリターン・リバーサルが挙げられます。簡単にいうと、成績の良し悪しは実力というよりは運によるものであるため、運というものが一定の水準ほど平等に(?)存在するのであれば、不運の後には幸運がくるというところでしょうか?でも、一定のスタイルを維持せずに、場当たり的(機動的とか臨機応変という表現もありますが)に行動しているものは対象外です。
2023年12月13日
確定拠出年金(その2)

以前、このブログで確定拠出年金のことに触れました。今後シリーズとして思いつくままに書いてみようと思っています。
前回の投稿のURLは以下のとおりです。
http://schole.chesuto.jp/e1704072.html
企業は一般的には、より良い人材(人財?)を求めます。何がより良いか企業が決めることなのでなんとも言えません。特殊な才能や創造性を求められることもあれば、素直に言うことを聞き、企業文化(もしくは因習?)に染めやすいということを求める企業もあるかと想像します。もちろん、職業に貴賤はないと思いますが、職種によっては人材に一定のスペック(例えば語学力とか専門知識、保有資格など)を求めるケースがあります。しかしながら、そういった基準を求めずに雇用の門戸を広げ、研修や職場での実地教育によって必要な人材を育てるという方法もあるかと思います。
所属する会社や職業、仕事に対する価値観、モーチベーションは様々です。目先の給料なのか、生涯所得なのか、はたまた意見が通りやすい風通しのいい会社なのか、とにかく安定しているかなどが挙げられるでしょう。それに対し企業は、誰でもいいから雇うというケースは別にして、優秀な人材や一定のスペックのある人材を求める場合、可能な限り、給与水準や企業文化(因習?しつこい?)、福利厚生などを高め、アピールしようとします。
いつものように話がそれたので元に戻しますが、大企業の場合、福利厚生(もしくは給与の後払い)として、厚生年金のほかにプラスアルファ部分として企業年金というものを設定・運用していることが多いです。社員教育などにそれなりに投資をして、長く在籍してもらうことを意図しているのかと想像する点で、退職金制度(これも要は給料の後払いかな?)と似ているのかと思います。最近では大企業でも、人材の流動性を勘案して退職金制度を廃止して、その分を毎月の給与に上乗せするところもありますね。そして前者の企業年金を確定拠出年金にする企業が割と増えてきました。これは、政府の同制度の整備が進んできたこともありますが、確定給付年金の場合、運用が芳しくなかったりすると損失部分がPL(損益計算書)の科目に出て含み損のような形で決算に影響与えるからではないかと思われるのと、市場環境が複雑かつ不安定となったことで、昔ながらの運用では成果を出しにくいため、ずいぶん前から流行っている(実際は人類が生まれてからそれが現実ですが)自己責任という言葉も追い風になったのかなとも思います。
以前、投資顧問業務に携わっていた時に、とあるグローバル大企業(製造業)の企業年金(私が担当したのはほんの一部分で数百億円くらい)が顧客でした。企業側の担当者は、元長期信用銀行出身者のいわゆるエリートさんでしたが、よく勉強をされており、説明が専門用語でも通じたので、とても助かった代わりに鋭い質問があって説明(言い訳?)に困ったこともありました。まあ、それなりの企業だと必要な部署に必要な人材を揃えているんだなあということを感じました。中規模の厚生年金だと、理事さんが現役を引退したお役人の老紳士だったりして、内容を理解していただくのに苦労した記憶があります。
また、在籍した会社が、確定拠出年金向けの投資信託を運用していたこともあり、同制度を採用している企業向けに投資教育やファンドの選定をしているコンサルタントと定期面談していたこともありますが、まだまだ新しい制度で、人材が不足しているらしく、特殊な運用手法を利用しているファンドだとなかなか理解していただけず、「自分が理解できていないものを、なぜ選んで、しかも顧客に勧めるのだろうか?」と疑問に思ったものです。
前置きのつもりが、書いているうちに長くなったので、今日のところはこれまでにします。次回はもっと、メリットやデメリットなど具体的なことを書こうかと考えています。特に私が現在運用している個人型(いわゆるiDeCo)が給与所得者以外にはご参考になるかと…
落ちではありませんが…「これが現実だ!」 (シャー・アズナブル風に)